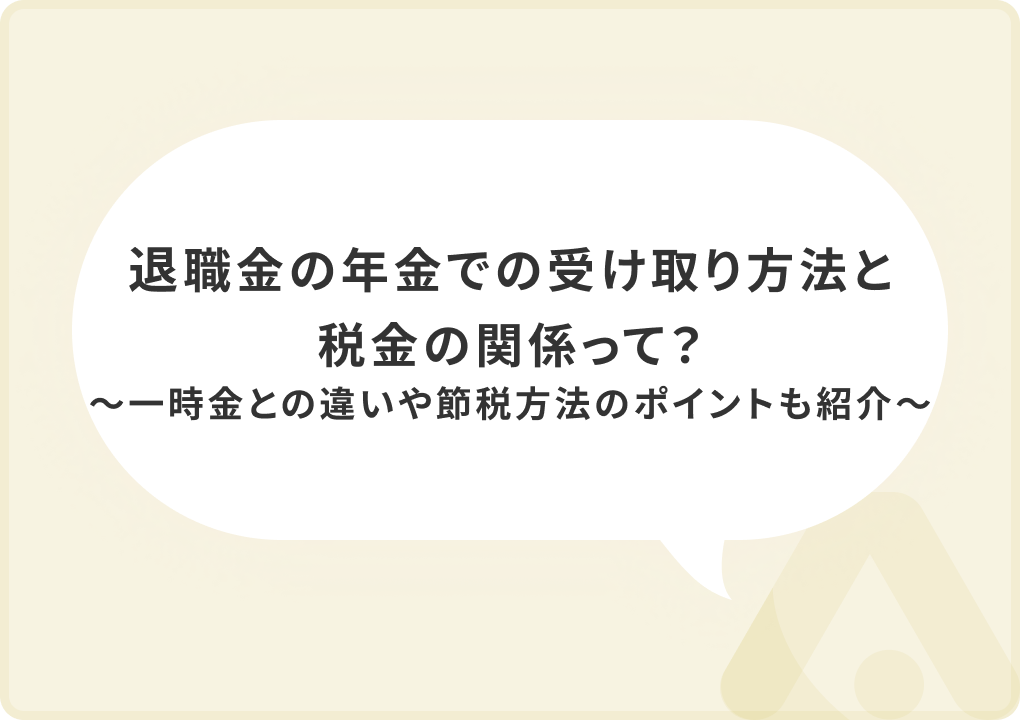
退職金運用



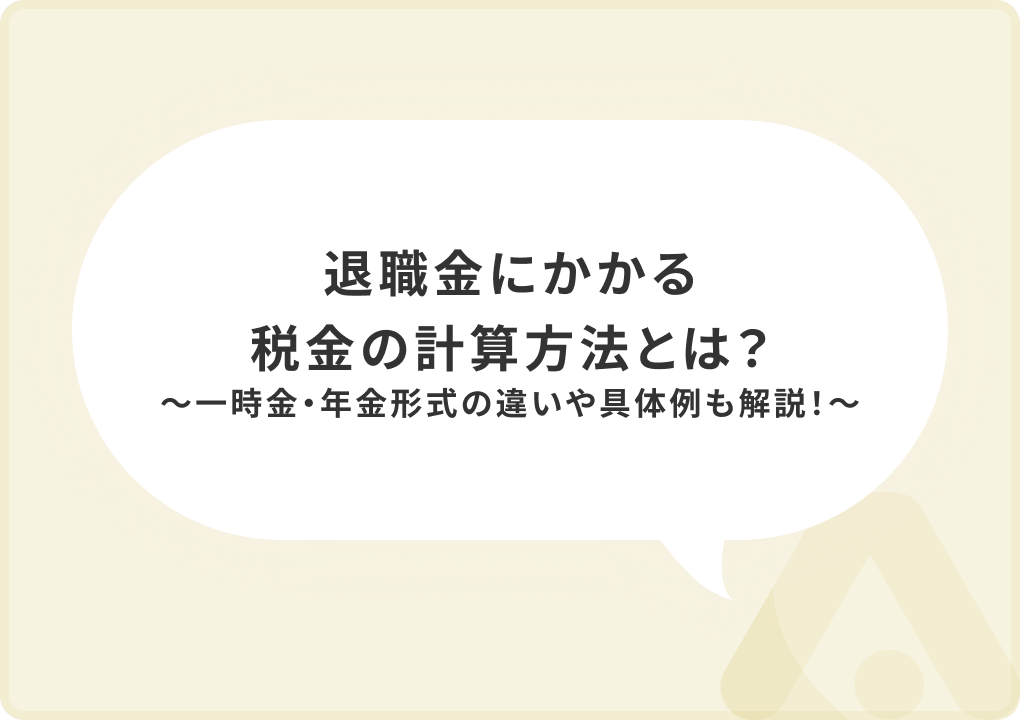
退職金は、長年の勤務に対するご褒美ともいえる大切なお金ですが、受け取る際には税金がかかることをご存じでしょうか?
本記事では、退職金にかかる税金の基本的な仕組みの情報から、計算方法や受け取り方による違い、具体的なシミュレーションの金額について詳しく解説します。将来の資金計画に不安がある方や、退職を控えている方はぜひ参考にしてください。
目次
退職金には、一般的な給与所得とは異なる優遇された税制が用意されています。そのため、受け取り時の税負担が抑えられる仕組みになっていることが特徴です。
ただし、「全額が非課税」というわけではありません。所得税や住民税がかかる仕組みになっており、特定の計算ルールに従って課税額が決定される点には注意が必要です。
退職金は、税法上「退職所得」という独立した所得区分に分類されており、給与や事業収入などとは異なる扱いを受けます。この退職所得は、その年に得た他の所得と合算されることなく、個別に課税額が計算されるのが大きな特徴です。
この仕組みにより、退職金だけに適用される特有の計算ルールや控除が使えるようになっています。
退職所得に対して課される税金は、主に以下の2種類です。
これらの税金は、退職金の支給時に企業が源泉徴収という形であらかじめ差し引いて納付するのが一般的な流れです。そのため、原則として受け取る側が確定申告を行う必要はありません。
退職金にかかる税金には、下記のような税制上の優遇措置が設けられています。
これらの制度は、長年働いてきた人への功労や、老後の生活を支える資金への配慮として設けられており、勤続年数が長いほど控除額も大きくなるように設計されています。これにより、長期勤務者ほど税負担が抑えられる仕組みです。
退職金にかかる税金の計算は、通常の給与所得とは異なり、特別なルールに基づいた独自の方式で行われます。
この章では、退職金の課税額を求めるための手順を3つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。
まず、退職金からどれだけの金額が課税対象になるのかを計算する必要があります。退職金の課税対象は「退職所得」と呼ばれ、以下の数式で求められます。
この計算式の最大のポイントは、控除額を引いたうえで、さらにその金額が2分の1に圧縮される点にあります。この仕組みによって、他の所得と比べても圧倒的に税負担が軽減されるようになっています。
退職所得控除とは、会社に勤務した年数に応じて決まる控除額です。
算出方法は下記のようになります。
【例】
勤続30年の場合:800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
つまり、退職金が1,500万円までは非課税となり、それを超えた分だけが課税対象になります。
この控除制度により、長く働いた人ほど税金が抑えられる仕組みが整えられています。
退職所得を計算したあとは、その金額に対応する所得税の速算表を使って税額を計算します。
下記は退職所得に関連する「所得税の速算表(2025年現在)」の一部です。
| 課税される退職所得 | 税率 | 控除額 |
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| ~330万円 | 10% | 97,500円 |
| ~695万円 | 20% | 427,500円 |
| ~900万円 | 23% | 636,000円 |
| ~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
この速算表を使って、算出した退職所得に対応する税率を適用し、所得税の金額を算出していきます。
また、所得税とは別に住民税(通常10%)も加算される点に注意が必要です。
退職金にかかる税金は、受け取り方の選択によって課税方式や適用される控除内容が変わるため、
最終的に手元に残る金額に大きな違いが生まれることがあります。主な受け取り方は以下の3種類です。
それぞれの税金の扱いやメリット・注意点を把握したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
退職金を一括で受け取る「一時金方式」は、もっとも一般的な受け取り方法です。
この方法では、退職金は「退職所得」として分離課税の対象となり、以下のような優遇措置が適用されます。
この方式の魅力は、まとまった資金をすぐに手にできる点にあります。住宅ローンの返済や投資、老後の資金確保などに柔軟に使いやすい反面、退職金の金額が高額になると税率も上がるため、税負担が大きくなる可能性もあります。
「年金方式」とは、退職金を毎年一定額ずつ分けて受け取るスタイルです。この形式では、退職金は「雑所得」に分類され、以下のような課税方法が取られます。
この受け取り方は、長期的に安定した収入を得たい人や、税率を抑えたい人に向いています。
ただし、退職所得に対しての控除や税額を半分に抑える特典は受けられないことに留意が必要です。
最近では、退職金を一部は一括で、残りは年金として分割で受け取る「ハイブリッド型」を選べる制度も増えています。この場合、それぞれの部分に対して個別に税金が計算されるため、ライフプランや資金ニーズに応じて柔軟に設計できます。
例えば
退職所得控除と公的年金等控除の両方を活用できる可能性があるため、税務面でも有利になることがあります。
ここでは、退職金の支給額と勤続年数をもとに、退職所得の算出からおおよその税負担額までを具体的にシミュレーションしていきます。ご自身の状況に近いケースを参考にすることで、退職後に受け取れる手取り額のイメージが掴みやすくなります。
将来のライフプランや税金対策にも役立ててください。
【想定条件】
勤続年数:15年
支給退職金:1,000万円
退職所得控除:40万円 × 15年=600万円
【計算の流れ】
退職所得 =(1,000万円 − 600万円)× 1/2
= 400万円 × 1/2 = 200万円
【課税の目安】
所得税(税率10%、控除97,500円):200万円 × 10% − 97,500円 = 102,500円
住民税(概算10%):200万円 × 10% = 200,000円
合計税額:約30万円/手取り:約970万円
【想定条件】
勤続年数:30年
退職金額:2,000万円
退職所得控除:800万円 +(70万円 × 10年)=1,500万円
【計算の流れ】
退職所得 =(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2
= 500万円 × 1/2 = 250万円
【課税の目安】
所得税(税率10%、控除97,500円):250万円 × 10% − 97,500円 = 152,500円
住民税(概算10%):250万円 × 10% = 250,000円
合計税額:約40万円/手取り:約1,960万円
【想定条件】
勤続年数:40年
退職金総額:3,500万円
退職所得控除:800万円 +(70万円 × 20年)=2,200万円
【計算の流れ】
退職所得 =(3,500万円 − 2,200万円)× 1/2
= 1,300万円 × 1/2 = 650万円
【課税の目安】
所得税(税率20%、控除427,500円):650万円 × 20% − 427,500円 = 872,500円
住民税(概算10%):650万円 × 10% = 650,000円
合計税額:約152万円/手取り:約3,348万円
h2 退職金と確定申告の関係
退職金を受け取ったあと、「確定申告って必要?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
基本的には企業側で税金が源泉徴収されるため、自分で手続きする必要はないのですが、いくつかの場面では確定申告が必要になる場合もあります。ここではそのポイントを詳しく解説します。
所得税や住民税は退職金の支給時に会社が自動的に徴収するため、原則として確定申告は不要です。
この退職所得申告の書類を退職前に会社へ提出していることが前提です。
この申告に関する書類を提出していれば、
が正しく反映されたうえで、税金が引かれています。
以下のような場合には、確定申告の申告が発生する可能性があります。
特に、申告書の提出がなかった場合は、退職金の全額が給与所得として課税対象となるため、税金が大幅に多く引かれている可能性があります。
実は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくるケースもあります。
例えば
このようなときは、「還付申告」をすることで、過剰に徴収された税金の一部が戻ってくる可能性があります。
還付申告は、退職した翌年の2月中旬〜3月15日までが一般的な受付期間です。
退職金に関わる税金は、計算方法やルールが複雑で疑問を抱く方も多い分野です。
ここでは、特によく聞かれる質問をピックアップして、わかりやすく回答します。
退職金に対する税金(所得税・住民税)は、支給と同時に企業側が天引きするのが一般的な処理です。つまり、受け取った金額はすでに税引き後の状態になっていることがほとんどです。
ただし、源泉徴収の正確な金額は、退職所得申告の書面を会社に提出しているかどうかによって大きく変わります。
この書類を提出していなかった場合には、本来よりも多めに税金が引かれている可能性があるため注意が必要です。
一概に「損」とは言えませんが、年金形式で受け取る場合は注意が必要です。
なぜなら、退職金が雑所得扱いとなるため、退職所得に認められている控除や軽減措置が受けられないためです。
ただし、年金形式で受け取る場合にも以下のようなメリットがあります。
そのため、「一括でもらって税率が高くなるよりは、分割して節税したい」という人には、年金形式が向いている場合もあります。ケースバイケースで損得が分かれるため、自身の収入状況・ライフプランに応じて選びましょう。
退職金に関する主な節税方法としては、以下の3点が挙げられます。
→これを出さないと、所得税が多めに源泉徴収されてしまいます。
→ 例えば「年内に退職金を受け取り、その受け取った年は他の収入を抑える」ことで、税率を低く抑えられる場合があります。
→ 退職金の一部を計画的に運用することで、トータルの資産効率を高められます。
また、「一時金と年金の併用」も、控除を上手く活用できれば税金を抑える手段の一つになります。退職金の節税は、選択を間違えると数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。不安な場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
退職金は通常の給与よりも税制上の優遇があり、退職所得の控除や1/2課税の仕組みにより税負担を軽減できます。ただし、受け取り方や申告の有無によって課税額は大きく変わるため、事前の理解と準備が重要です。一時金・年金形式・併用パターンそれぞれにメリットがあり、ライフプランに応じた選択がカギとなります。シミュレーションや節税対策も含め、退職金の受け取り方を検討しましょう。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。