
投資基礎知識



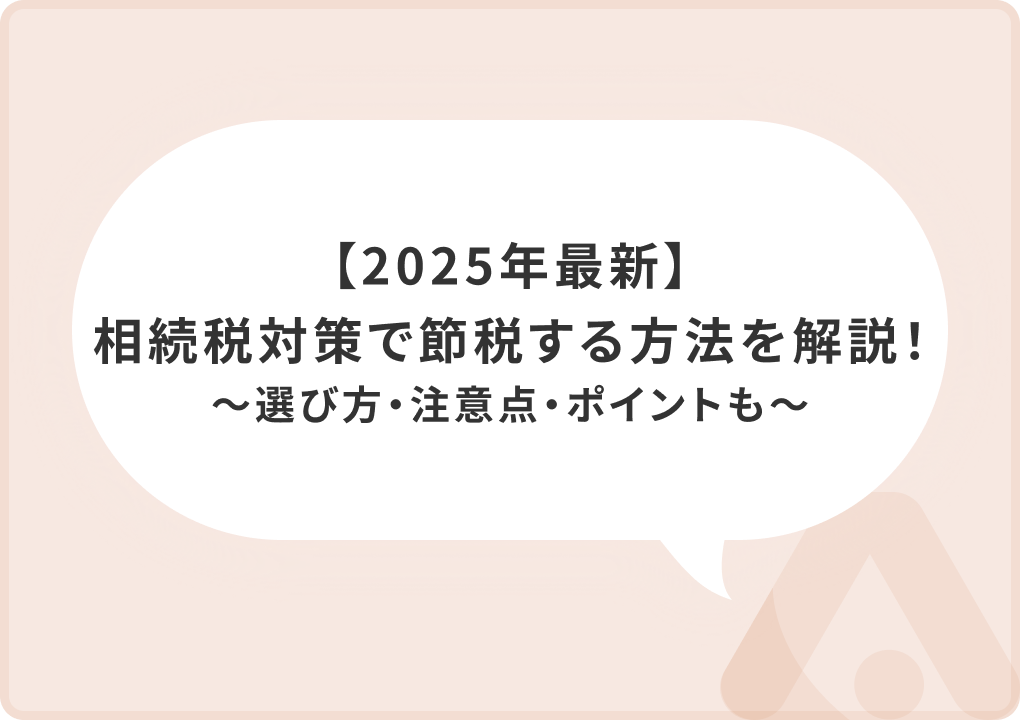
相続税の額は、準備や対策を怠ると予想以上に膨らむ可能性があります。生前からどのような方法を選び、何に注意すべきかを知っておくことで、税額を大きく減らすことが可能です。本記事では、相続前に行うべき節税対策について解説し、遺産やお金の活用法、効果的な方法や注意点を詳しく紹介していきます。
目次
相続税対策と聞くと、富裕層だけに関係ある話だと思っていませんか?
ここでは、そもそもなぜ相続税対策が必要なのかについて解説していきます。
相続税とは、亡くなった方が残した財産にかかる税金です。
財産には現金や預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。
相続税は、相続財産が基礎控除額を超える場合に課税され、その税率は財産の額が多いほど高くなります。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
この基礎控除を超える部分に税金がかかるため、多額の遺産を残す場合は相続税対策が必要になることが多いです。
相続税の税率は10%から55%と非常に高いため、財産が多い場合は大きな負担になります。
適切な相続税対策をすることで、財産を効率的に分割し、税金の負担を抑える方法を見つけられます。
例えば、基礎控除を最大限活用できるよう相続人を増やしたり、生前贈与を活用して相続財産を減らしたりする方法があります。また、不動産の相続税評価額を下げる取り組みも有効な手段です。
相続は財産を分け合うだけの手続きではなく、相続人同士の合意が必要です。
この過程で、財産の相続税評価額を概算しておくことが大切です。
特に不動産や事業用資産のように分割が難しい財産が含まれる場合、このリスクはさらに高まります。
遺言書の作成や財産の分割計画を早めに立てることは、相続人の負担を減らし、スムーズな相続を実現する第一歩です。
相続税対策を進めるためには、いくつかの重要な準備を行う必要があります。
相続税対策を進めるにあたって、まず取り掛かるべきは財産目録の作成です。
財産目録とは、現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続対象となるすべての財産をリスト化したものです。
この過程で、財産の相続税評価額を概算しておくことが重要です。
不動産など価値が変動しやすい資産については、専門家に相談して正確な評価を行うのがおすすめです。
これにより、財産総額を把握でき、相続税対策を立てるための基礎を築けます。
次に進めるべきは相続人の確認です。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わるため、誰が相続人になるのかを確定することが大切です。
法定相続人とは、民法上定められた相続権を持つ配偶者や子どもなどのことを指します。
また、養子縁組を活用することで法定相続人を増やし、基礎控除額を引き上げる方法もあります。
しかし、養子縁組には法的な手続きや制限があるため、専門家に相談しながら進めることが必要です。
財産評価額を低く抑えることや、非課税枠を活用することも相続税対策の基本です。
不動産については「小規模宅地等の特例」が利用できる場合があり、この特例により不動産の相続税評価額を大幅に下げられることがあります。
また、生命保険の非課税枠の活用も有効な方法です。
非課税枠や特例の適用を受けるには条件があるため、財産の種類や相続状況に応じて最適な組み合わせを考える必要があります。
これにより、相続税の負担を大幅に軽減できます。
ここからは、相続税の負担を軽減するために有効な具体的な対策方法を一つずつ見ていきましょう。まずは、生前に計画的に財産を移転できる「暦年贈与」について解説します。
暦年贈与とは、生前に一定額を非課税の範囲で贈与することで、相続財産を減らし、最終的な相続税負担を軽減する方法です。
この方法により、贈与税の基礎控除を活用しながら、少しずつ財産を移転できます。
暦年贈与は、資産を早めに子や孫へ分配する手段として広く用いられています。
また、贈与された資産が長期的に活用できる点もメリットといえます。
暦年贈与では、年間110万円までの贈与に対して贈与税が発生しない「基礎控除」を活用します。
この非課税枠内で毎年計画的に贈与を行うことで、大幅な相続税の軽減が期待できます。
たとえば、子や孫に毎年110万円を贈与することで、長期にわたり相続税評価に影響する財産を減らせます。
ただし、基礎控除額を超える贈与を行った場合は贈与税が課されるため注意が必要です。
2024年の税制改正により、生前贈与が相続開始前7年間に行われた場合、その贈与額は相続財産に加算されることになります。
これまでは3年間が適用期間でしたが、2024年から徐々に加算対象期間が延び、完全に7年間の加算となるのは2031年以降の相続開始時です(2024年中の贈与は1年分、2025年中の贈与は2年分…と加算期間が増えていく)。
この改正の影響で、相続税の計算における生前贈与の扱いが厳格化されます。
そのため、相続税対策を行う際には、計画的に暦年贈与を活用し、相続税負担の軽減を目指すことがより重要です。
また、税制改正に伴い、早めの準備がますます必要になるでしょう。
生前贈与の方法としては、暦年贈与の他に「相続時精算課税制度」があります。
相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与しても、その時点では贈与税を控除・軽減し、相続時に精算する仕組みです。
この制度を活用することで、贈与時には高額な贈与税を支払う必要がある場面でも、贈与税の優遇措置を受けることで実質的な負担を減らせます。
贈与した財産は最終的に相続時に合算して相続税を計算するため、相続財産全体に対する公平性も保たれています。
財産の相続税評価額を抑える工夫として有効な相続税対策方法の一つです。
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税となる特別控除が設けられています。この控除額を利用することで、事前に親から子や孫へ財産を移転させ、相続財産を圧縮できます。特別控除は累計額で計算されるため、多額の財産を一括贈与する際にも有効です。
ただし、贈与した財産は相続開始時に計算に加算されるため、計画的な贈与が必要です。
また、相続時精算課税制度を利用することで財産の評価方法が固定される場合があり、対象財産の評価額をしっかり把握しておくことも大切です。
2024年の法改正では、相続時精算課税制度に新たに年間110万円の基礎控除が加えられたことにより、相続税対策の選択肢が広がります。
この改正により、特別控除額の範囲内で贈与を行った場合でも、追加の税制優遇を受けやすくなります。
なお、年間110万円の基礎控除枠内の贈与は、2,500万円の特別控除枠とは別枠で、かつ相続時に相続財産への加算対象となりません。
そのため、年間110万円以内の贈与額には贈与税が課税されない仕組みを活用し、財産を効率的に移転させることができます。
この変更は、より柔軟な贈与計画を立てやすくなるでしょう。
ただし、各制度を適切に組み合わせるには専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
相続財産に不動産が含まれる場合、その評価額を適切に管理・活用することが相続税対策の重要なポイントになります。
ここでは、不動産を活用した相続税評価減の方法について詳しく解説します。
相続税対策の方法として、不動産の評価減はよく活用されます。
通常、相続税を計算する際には不動産の「相続税評価額」が基準です。この評価額は市場価格(時価)よりも低めに設定されることが多く、これが不動産を活用した節税対策の大きなポイントです。
不動産の相続税評価額は、宅地や建物、賃貸物件など、それぞれの種類に応じた方法で評価されます。
そのため、財産の全体的な評価額を下げ、相続税の負担を軽減できます。
「小規模宅地等の特例」は、不動産を利用した代表的な相続税対策の一つです。
この特例を活用することで、自宅や事業用地などの土地に対する相続税評価額を大幅に減額できます。
たとえば、居住用宅地で最大330㎡までの部分であれば、相続税評価額が最大80%減額されます。
ただし、この特例を適用するには、相続人がその土地を継続利用することや特定の要件を満たす必要があります。
このように条件さえ整えば、非常に大きな節税効果を得られるため、事前の確認が大切です。
「貸家建付地」とは、借りている人が住む建物や使用する土地のことを指します。こうした不動産は、相続税評価額が低く評価される場合があります。
例えば、貸家建物に係る土地の評価額は、自用地としての評価額に一定の控除率を適用して算出されるため、節税効果を期待できます。
また「貸家評価」とは、建物そのものに賃貸契約による制約があるため、通常よりも評価額が下がるという仕組みです。
これらを適切に活用することで、評価額を減らし、相続税額を抑えられます。
生命保険を活用することで、税負担の軽減や納税資金の準備など、様々なメリットが得られます。
生命保険は、相続税対策の方法として非常に有効です。
生命保険金には、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠が設けられており、この枠を活用することで相続税の負担を軽減できます。
この非課税枠は、現金や預貯金といった他の財産とは別に計算されるため、生命保険に加入することで財産の評価額を抑えられます。
たとえば、法定相続人が3人いる場合、最大で1,500万円までの生命保険金が非課税となり、現金を遺すよりも効率的に相続対策が進められます。
生命保険は、単に非課税枠があるだけでなく、納税資金の準備手段としても役立ちます。
相続税の納税期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内と非常に短いため、不動産などの換金が難しい財産を多く所有している場合、現金資産が不足するケースもあります。
死亡保険金は、契約後速やかに受け取れるため、納税資金への活用がしやすい点がメリットです。
これにより、財産を急いで売却することなく、スムーズに納税を完了できます。
生命保険を適切に活用することは、財産の維持と相続税の負担軽減の両方を実現する手段となります。
法定相続人の数を増やすことも、相続税の基礎控除額を増やし、結果として相続税負担を軽減する対策の一つになります。
ここでは、養子縁組を活用した対策について解説します。
養子縁組は、血縁関係のない人や、血縁関係のある親族を法的に家族として迎える手続きです。特に相続税対策として活用される場合、養子を法定相続人に加えることで相続税の基礎控除額を増やす効果が期待できます。
この手続きにより相続人が増えることで、一人あたりの課税対象額が抑えられ、結果的に相続税負担を軽減できます。
ただし、節税目的のみの養子縁組は税務署に否認されるおそれがあるため、慎重に手続きを進める必要があります。
養子縁組をすることで、相続税の基礎控除額が増えます。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、養子を増やすことで基礎控除の総額が拡大します。
例えば、養子縁組によって法定相続人が1人増えるごとに600万円が上乗せされるため、相続税の課税対象となる財産を減らす効果があります。
さらに、生命保険金の非課税枠も法定相続人の数に応じて計算される仕組みになっているため、養子縁組をすることでこの枠を活用する機会が広がります。
例えば、「法定相続人1人につき500万円の非課税枠」が設定されており、養子を増やすことで非課税の生命保険金額が大きくなる可能性があります。
ただし、実子がいるケースでは、養子の数が税務上認められる範囲(実子がいる場合1人、いない場合2人)に制限されているため、事前に確認することが大切です。
ご自身の財産を、信頼できる家族などに託して管理・運用してもらう「家族信託(民事信託)」を活用することで、相続税対策につながります。
家族信託や民事信託は、信頼できる家族や第三者に財産を託して管理・運用してもらう仕組みです。
この制度を利用することで、相続税対策や財産管理を円滑に進められます。
信託を設定することで、遺産分割に伴うトラブル防止や財産評価の工夫ができ、相続税の負担を軽減するための有効な手段です。
家族信託では、受託者が財産の管理者として役割を担うので、所有者が高齢になったり体調を崩しても確実に財産が正しく運用されます。
特に不動産の管理が必要な場合にこの仕組みは優れた効果を発揮します。
財産管理をスムーズに行うことで、必要な資金を確保しながら相続税の影響を最小限にとどめられます。
二次相続とは、配偶者が他界した後に発生する別の相続を指します。
家族信託を用いることで、二次相続時の財産の配分を明確に指定でき、相続人間のトラブルを防止できます。
この対策を講じることで、全体の相続税の負担を最小限に抑えつつ、財産のスムーズな移転を実現します。
高齢化が進む現代では、相続人や財産の所有者が認知症になる可能性が高まっています。
認知症になった場合、法律上は財産管理が大きく制約されるため、相続税対策が進めにくくなります。
家族信託を活用することで、認知症のリスクを見越した柔軟な財産運用ができ、相続に伴う煩雑な手続きを防げます。
遺産分割を円滑に進め、「争族」を防ぐために欠かせないのが遺言書です。
ここでは、遺言書作成の重要性と種類について解説します。
相続税対策では遺言書作成が非常に重要です。
遺言書を活用することで遺産の分割方法を明確に指示でき、相続人間での「争族」を防ぐ効果があります。
例えば不動産の相続では、各相続人が共有する場合にトラブルが生じやすいため、遺言書を事前に作成して分割方法を決めておくことが大切です。
遺産分割を指定することで、各相続人ごとの相続税負担を予測しやすくなり、納税資金の計画を立てられるようになります。
また、遺産の分け方を適切に設計することで、基礎控除や非課税枠を最大限に活用でき、多額の財産が課税されることを防げます。
このように、遺言書による分割指定は相続税対策の有効な方法です。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれメリットとデメリットがあるため、相続税対策を検討する際にはどちらが適しているかを判断する必要があります。
自筆証書遺言は、自分で遺言書を全文手書きして作成する方法です。
費用がかからず手軽に作成できるため、利用しやすい方法ですが、形式に不備がある場合や、第三者によって改ざんされるリスクがあります。
さらに、遺言書が見つからなかった場合は効力を発揮しない可能性もあるため、注意が必要です。
一方、公正証書遺言は公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成する方法です。
記載内容が法律に則っているため無効になるリスクが低く、改ざんされるリスクもありません。
加えて、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、遺言書が見つからないという事態も防げます。ただし、手続き費用がかかる点と、事前に財産目録や家族構成を整理する必要がある点が課題です。
いずれの方法を選ぶにせよ、適切な遺言書の作成は相続税対策に必要不可欠なステップです。
相続財産の評価や家族関係の状況を踏まえた上で、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続税対策は、できるだけ早い段階で始めることが大切です。
その理由はいくつかありますが、まず、相続税の負担を軽減するには時間をかけて計画的に財産を評価し、有効な対策を講じる必要があるからです。
例えば、生前贈与を活用して財産を徐々に移転する方法では、年間110万円の基礎控除額を毎年適用することで効果的に相続財産を減少させられます。
このような方法を取り入れるには十分な準備期間が必要です。
また、相続財産の評価には不動産や現金など多種多様な資産が含まれるため、適切な手続きをするには時間と労力が必要です。
不動産を活用した評価減を行う場合、税務上の確認や物件の組み換え、貸家建付地の活用など、事前準備が不可欠です。
それらを早めに整えることで、スムーズに効果的な節税へとつなげられます。さらに、相続税対策を早く始めることで、家族間での話し合いに十分な時間を設けられます。
これにより、財産分配について認識を一致させ「争族」を防ぐ上でも有効です。
適切な財産の分割計画を立てることで、相続トラブルを未然に防げるでしょう。
相続税対策に取り組む場合、最終的には専門家のサポートを受ける必要がありますが、早めに着手することで、税理士など専門家に相談する余裕も確保できます。
それによって、相続税の軽減効果を最大限に活用できます。
この記事でご紹介したように、相続税対策には様々な方法があり、ご自身の状況によって最適な選択肢は異なります。
「どれを選べばいいのか分からない」と迷った時に、誰に相談すべきかについて解説します。
相続税対策方法には多くの選択肢があり、相続財産の内容や相続人の状況によって適切な対策が異なります。
例えば、不動産を活用した評価額の圧縮や生前贈与を活用して相続税を減らす方法などがありますが、それぞれにメリットやデメリットがあり、注意点も多いです。
そのため、どの方法を選ぶべきか迷った場合は、まず税理士に相談することをおすすめします。
税理士は相続税の専門知識を持っており、財産の評価から適切な対策の選定まで、個々の状況に応じたアドバイスをしてもらえます。特に、税制が頻繁に改正されるため最新の情報を把握するのは容易ではなく、専門的な視点が必要です。
相続税対策を適切に行うには、早めの準備が必要です。
そして、税理士に相談することで、相続税の軽減だけでなく「争族」の予防や円滑な遺産分割計画の作成もできるようになります。
迷った際には、ぜひ専門家の力を借りて、最適な対策を見つけてください。
相続税対策は、財産の負担を軽減し、相続人同士のトラブルを防ぐために必要不可欠です。
生前贈与や不動産の評価減、生命保険の活用などのさまざまな方法を組み合わせることで、相続税の負担を抑えられます。
それぞれの方法には特徴や注意点があるため、自身の財産や家庭環境に合った対策を選ぶことが大切です。
相続税対策を実行する際は、財産目録の作成や評価額の概算を行い、法定相続人や非課税枠を把握することが第一歩です。
また、2024年の法改正による制度の変更点を把握しながら計画を進めましょう。
節税効果を最大限に引き出すには、専門家である税理士や相続コンサルタントへの相談を早めに行うことをおすすめします。
早期からの準備と戦略的な方法の活用により、相続税の負担を軽減し、スムーズな相続手続きを実現させましょう。
対策を怠ると、財産評価が適切に行えず、思わぬ負担やトラブルが発生する可能性もあります。
適切な対策の実現には計画性と専門知識が重要ですので、ぜひ早い段階で行動を起こしましょう。
ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。