
投資基礎知識



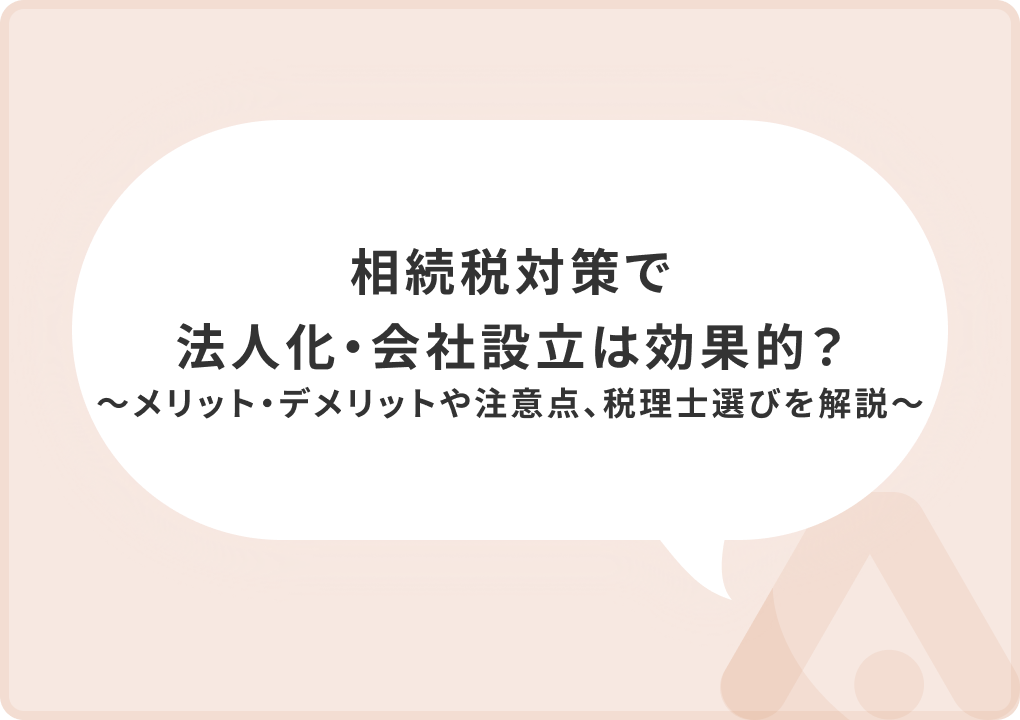
相続税対策として法人化が効果的か気になりますよね。特に不動産賃貸業など、事業を営む方にとって、将来の相続税負担は大きな懸念点です。個人として資産を所有し続けるべきか、それとも法人化することでどのようなメリット・デメリットが生じるのか、複雑で判断が難しい問題です。
本記事では、相続税対策における法人化が効果的なのかについて解説します。法人化によるメリット・デメリットについても詳しく触れていきます。
目次
なぜ法人化が相続税対策につながるのでしょうか?
ここでは、個人と法人における財産評価や相続対象の違いについて解説していきます。
相続税対策として法人化が注目される理由の一つに、個人と法人では財産の評価方法が異なるという点があります。
個人の場合、相続の対象となる財産(たとえば不動産や預貯金、事業資産など)は、そのままの市場価格や評価額で相続税が計算されます。
一方、法人が所有する財産については「株式」という形で評価され、非上場株式の場合は資産価値そのものよりも低い評価が適用されることがあります。
法人化することで、財産全体の評価額を抑えることができ、結果として相続税負担を軽減できます。
この評価の違いを踏まえると、法人化は非常に効果的な相続税対策と言えるでしょう。
個人が所有する財産を法人化することで、相続の対象が「個人の財産」から「法人の株式や出資持分」に変わります。
たとえば、不動産を法人名義に移転した場合、不動産自体ではなく法人が発行する株式や出資持分が相続の対象になります。
株式の評価額は、法人の収益や資産内容に基づいて算出されるため、場合によっては実際の資産価値よりも大幅に低くなることがあります。
このように、株式評価を用いることで相続財産全体を圧縮し、相続税の負担を減らせます。
法人化を通じてこうした仕組みを活用することは、効率的な相続税対策の一つと言えます。
法人化により発行された株式や出資持分を活用することで、相続税および贈与税を軽減する効果があります。
法人所有の財産評価が低く抑えられることで、株式自体の評価額も圧縮され、親から子へ株式を生前贈与する際の贈与税を軽減できます。
また、非課税枠を活用して計画的に少しずつ移転することで、相続税負担をさらに抑えることができます。
さらに、遺産分割の際も、現金や不動産ではなく株式で分配することで、複雑な相続手続きを簡略化できるのも大きなメリットです。
法人化を適切に活用することが、相続税や贈与税の効率的な対策につながります。
ここでは、法人化による相続税対策のメリットについて解説していきます。
法人化による相続税対策の魅力の一つは、不動産等の評価を圧縮することで、相続税の負担を軽減できることです。
不動産を個人で保有している場合、その評価額は市場価格や固定資産税評価額をもとに算出されます。
一方、法人が不動産を所有した場合、非上場株式の評価額として算出されるため、株価算定の際に実際の資産価値よりも低く評価されることがあります。
この評価額の引き下げにより、相続税負担が大幅に軽減される場合もあります。
また、相続財産の総額を減らすことで、課税遺産総額が相続税の基礎控除額以下になる場合もあり、相続税そのものが発生しないケースもあります。
特に、不動産を複数所有している方には法人化が有効な対策方法の一つとして検討されます。
法人化することで、相続税対策として「株式の生前贈与」ができます。
個人が所有する財産を生前贈与する場合、そのままの財産価値で課税対象となりますが、法人設立後の株式を相続人へ贈与する場合は、法人が保有する資産の評価額を反映した株式評価額が課税対象になります。
また、非上場株式は上場株式と異なり取引相場がないため、財産価値がそのまま課税評価額に反映されないことがあります。
この特性をうまく活用することで、生前贈与にかかる贈与税を軽減しつつ、事前に相続対策を進められます。
さらに、株式の分配による資産移転を進めることで、相続人間で公平な財産分与が実現しやすくなるのもメリットです。
ただし、株式贈与の際には適切な評価のもと進める必要があるため、税理士など専門家への相談も欠かせません。
法人化を行うことで、相続発生後の遺産分割手続きをシンプルに進められるメリットもあります。
個人財産の場合、相続が発生した際に各財産を相続人間で分割する必要があり、内容によっては合意形成に時間がかかることも少なくありません。
一方で、法人化を通じて財産を法人に集約し、相続人が法人の株主となる仕組みを作っておけば、遺産分割の対象は法人の株式のみになります。
特に、不動産や事業資産など分割が難しい財産が多い場合、法人化を進めておくことでトラブルを回避し、スムーズに相続手続きを進められます。
また、財産を法人に集約することで管理が一元化されるため、相続後の資産運用や経営の方向性についても無駄なく調整しやすくなります。
相続税対策以外の法人化によるメリットは、以下の通りです。
法人化を通じて所得を分散することで、個人の所得税・住民税の負担を軽減する効果があります。
例えば、家族を法人の役員として選任し、役員報酬を支払うことで、所得が家族間で分散され、全体の税率が抑えられる仕組みです。
相続税対策だけでなく、現金のフローを最適化する方法としても有効です。
この方法を実践するためには、税法の知識が必要になるため、経験豊富な税理士の協力が大切です。
法人化すると、個人事業主のときよりも経費として認められる範囲が広がります。
たとえば、法人の業務に関連する会議費や交際費、車両費などが経費として計上できます。
また、一定の条件を満たせば、役員報酬や退職金も経費に含まれるため、個人の年間所得を抑えるとともに法人の利益を調整する形で節税できます。
これにより、必要経費を効率的に活用しながら財産の管理がしやすくなります。
会社を設立した場合、資本金を1,000万円未満に抑えることで、原則として設立後最初の2期は消費税の納税義務が免除されます(一定の要件を満たす場合)。
この免税期間を活用することで、事業の初期コストを軽減し、資金を有効に運用できます。
また、免税を受ける期間中に財産の移転や事業計画の見直しを行うことで、長期的な相続税対策の計画を立てる余裕も生まれます。
法人では、事業の赤字が発生した際に損失を繰り越して翌期以降の利益と相殺する「繰越控除」が認められています。
この控除期間は個人事業主の場合よりも長く、法人の場合は最長10年間適用されます。
この仕組みにより、事業経営が傾いた場合でも所得税の負担を軽減できるため、事業を続けやすくなります。
損失が気になる場合にも、税理士の助言を得ながら計画的に対応することが大切です。
法人化によるデメリットや注意点は、以下の通りです。
法人化による相続税対策はメリットが多い一方で、法人設立や維持にはさまざまなコストが発生します。
法人設立時には定款の認証費用や登録免許税などの初期費用が必要です。
また、法人を維持するための会計処理や決算書作成には税理士への依頼が必要になる場合が多く、その費用も考慮しなければなりません。
さらに、法人には地方税等の固定的な税金が課されます。
このように、相続税対策を目的として法人化を検討する際には、これらの維持コストが全体の資産プランにおいて負担にならないか、十分に検討が必要です。
法人化を行うことで、さまざまな事務手続きが発生します。
法人設立時は定款の作成や登記申請が必要で、これらについては法律上の形式やルールに従わなければなりません。
また、設立後も税務申告や帳簿の作成、社会保険の手続きなど、継続的に複雑な事務作業が発生します。
個人での管理と比較して業務が煩雑化するため、税務や法務に詳しい専門家のサポートを依頼することが欠かせない場合が多くあります。
このような事務手続きの煩雑さは、法人化のデメリットの一つです。
法人化している場合、赤字になった場合でも一定の税金を支払わなければなりません。
具体的には、法人住民税の一部である「均等割」が赤字でも課税されるため、利益の有無に関わらず税金負担が発生します。
このため、相続税対策のために法人を設立する場合には、法人としての収益性を維持する方法も十分に検討しておく必要があります。
税金の計画は節税を目的とする相続税対策において非常に重要なポイントなため、税理士と連携して細かく調整することをおすすめします。
法人化すると、役員や従業員は原則として社会保険への加入が義務付けられます。
これは法人の代表者である個人にも適用されるため、これまで国民健康保険や国民年金に加入していた場合と比較して、支出が大幅に増加することがあります。
社会保険料の負担額は収入額に比例するため、法人の報酬設定によっては大きなコストとなる可能性があります。
特に小規模の法人にとっては、この負担が経営を圧迫する要因となる可能性があるため、事前にどの程度の負担が発生するのかを把握した上で法人化を検討することが大切です。
相続税対策として法人化が有効になるケースは、どのような時なのでしょうか。
不動産を複数所有している場合、法人化は効果的な相続税対策の一つです。
不動産はその評価額を適正に管理することが大切で、法人を活用することで財産評価額を圧縮できる場合があります。
たとえば、通常の個人所有での不動産相続では、物件ごとの時価評価や路線価などが基準になりますが、法人の所有となることで、株式としての評価になるため、相続税が軽減されます。
また、法人化することで賃貸不動産などから得られる収益を法人の収益とみなすことができ、個人の所得を圧縮する形で節税につなげられます。
不動産を適切に法人へ移転し、家族や相続人を法人の役員や株主にすることで、相続後のトラブル回避や財産分割の円滑化も期待できます。
こうした方法を活用するためには、専門知識を持つ税理士への相談が欠かせません。
事業を所有・運営している経営者にとって法人化は相続税の節税効果を得るためだけではなく、事業承継をスムーズに進めるための有効な方法です。
事業を個人で所有している場合、相続時に事業用資産が直接的に相続税の課税対象になり、事業資産の売却や借金を余儀なくされるケースもあります。
しかし法人化することで、事業用資産を法人に移行し、相続時には法人の株式を承継の対象とすることにより、相続税の負担を抑えられます。
さらに、生前に法人の株式を少しずつ贈与することで、相続税の課税対象となる財産を計画的に圧縮できます。
この「株式の分散」を行うことで、相続人一人あたりの課税額を軽減することもできます。
ただし、株式の評価額の算定には専門的な知識が必要なため、事前に適切な対策を立てる必要があります。
事業承継を成功させるためには、法人化のメリット・デメリットを十分に理解し、相続税対策に精通した税理士と連携して進めることをおすすめします。
法人化を相続税対策として検討する際には、いくつかの注意点があります。
法人化を通じて相続税対策を行う場合、資産を個人から法人に移転する際の「みなし譲渡所得税」が課される可能性があります。
これは、資産の移転時にその時点での時価が基準となり、譲渡が成立したとみなされることによって課税対象となります。
特に、不動産や株式など資産価値が大きい場合、高額な所得税負担が発生することがあります。
そのため、相続税対策を目的とした法人化を検討する際は、移転する資産の種類や評価額をしっかり確認し、負担がどの程度になるのか見積もる必要があります。
法人化を行う際、相続税対策の一環として非上場株式の評価を低く抑えることを目的に進めるケースを多く見かけます。
しかし、株式評価にはさまざまな評価方法が適用され、例えば純資産価値や取引相場、将来の収益などが考慮されるため、予想外の高い評価額がつくことがあります。
これにより、相続の際にかかる相続税が想定よりも軽減されないケースもあります。
法人化を進める前には、慎重に相続税専門の税理士に相談し、株式評価額のシミュレーションを行うことが大切です。
法人化による相続税対策では相続税以外にも法人税や所得税が深くかかわります。
例えば、法人化した場合には法人税や法人住民税が課されるため、会社の収支状況に応じて適切な税務処理が必要です。
また、法人から役員報酬を受け取る場合には所得税が生じ、適切な分配割合を考える必要があります。
さらに、相続の際には株式の移転が課題となるため、相続税の精査も欠かせません。
こうした複数の税目を総合的に理解し、適切に対応するためには、税務や相続に詳しい税理士のサポートが非常に大切です。
専門家の助言を得ることで、最適な相続税対策を講じる準備ができます。
実際に相続税対策として法人を設立するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
法人化を進める際には、まず事業計画を策定する必要があります。
事業計画では、法人の目的や運営方針、収益計画、資金計画などを明確にします。
特に相続税対策を目的とする場合、法人を通じてどのように財産を管理し、相続税を軽減するのか具体的な方向性を示すことが重要です。
また、不動産を管理する資産管理会社か、一定の事業収入を得る営業会社かといった法人形態を決めることも含まれます。
次に、法人の定款を作成します。
定款は法人の根本規則であり、法人名、所在地、事業目的、役員構成、株式の取り扱いなどを記載します。
相続税対策を目的とする場合、株式の分散や家族構成員の役員としての選任方法についても考慮し、適切に記載する必要があります。
作成した定款は、公証人役場で認証を受け、公的に有効な文書となります。
定款認証後、法人設立時に決定した資本金を銀行口座に払い込みます。
この時点で法人名義の銀行口座はまだ作成できないため、発起人(法人設立を主導する者)の個人名義の口座を利用します。
資本金の額は、相続税対策の観点から慎重に設定する必要があります。
例えば、資本金を1,000万円未満に設定することで、設立後の一定期間、消費税が免除されるメリットが得られる可能性があります。
次に、法人設立登記を法務局に申請します。
設立登記では、会社の基本情報や役員構成、定款の内容、資本金などを記載した必要書類を提出します。
この手続きが完了することで、法人が正式に設立され、法的な権利義務が生じるようになります。
法務局への申請過程では正確な記載と迅速な手続きが必要なため、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。
法人設立が完了したら、税務署や市区町村役場に対して必要な届出を行います。
具体的には、法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを提出します。
これら届出を怠ると税務上の不利益が生じる可能性があるため、注意が必要です。
特に相続税対策を目的として法人化を行った場合、管理財産や役員報酬、株式の移転に関する税制上の届出を正しく行うことが欠かせません。
法人化を活用した相続税対策は、高額な相続税負担を軽減する有効な方法の一つとして注目されています。
法人化を通じて、財産の評価を引き下げたり、その分散を図ることで、相続財産の総額を抑えることができます。
また、法人を活用すれば不動産や株式などの資産の管理や移転が簡略化され、生前贈与もスムーズに行えます。
しかし、相続税対策として法人化を選択する際には、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。
例えば、法人化には設立や運営にコストがかかるほか、法人設立後も事務手続きが煩雑であり、さらに赤字でも税金が発生する場合があります。
また、法人設立時に資産を移転した場合、「みなし譲渡所得税」が発生するリスクもあるため、慎重な検討が必要です。
こうしたメリットやデメリットを踏まえた上で、法人化を相続税対策として最大限に活用するには、税務に関する専門的な知識が欠かせません。
相続税や法人税、所得税など複数の税目が絡むため、ご自身で判断するのではなく、経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。
税理士は、個別の資産状況や家族構成に応じた最適な相続税対策を提案し、手続きのサポートを行います。
相続税の負担を軽減し、ご家族の将来に備えるためにも、会社設立を用いた相続税対策には、専門家の協力が大切です。
ぜひ信頼できる税理士とともに、効果的な相続税対策を進めていきましょう。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。