
投資基礎知識



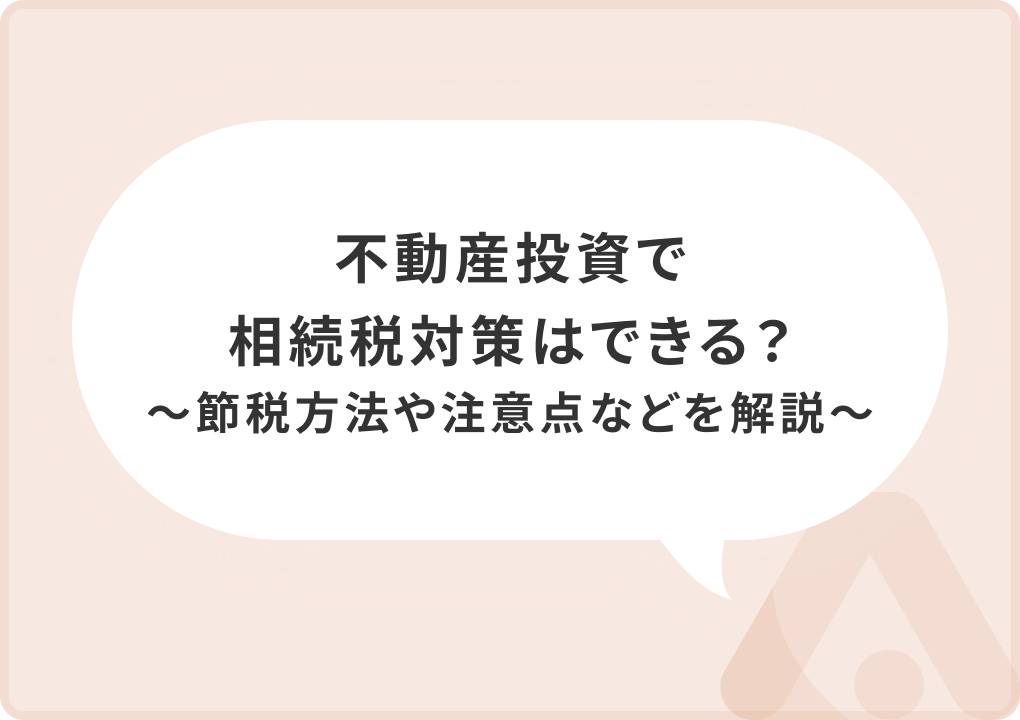
相続が発生したとき、現金よりも不動産のほうが相続税の評価額が下がるため、相続税対策として有効です。しかし、投資として不動産を活用する場合、注意すべき点も多くあります。本記事では、不動産投資を活用した相続税対策の効果や節税方法、評価額の仕組み、注意点について詳しく解説します。
目次
不動産投資を活用すると、相続税対策に効果的な理由はいくつかあります。
不動産の相続税評価額は、実勢価格(市場価格)よりも低くなります。
土地については「路線価方式」や「倍率方式」によって評価され、例えば市街地の土地であれば、公示地価の約80%に相当する額が評価額となるのが一般的です。
路線価方式は、主に市街地にある土地の評価に用いられ、路線価(道路に面した宅地の1平方メートルあたりの評価額)にその土地の面積をかけて計算します。
路線価は、公示地価の80%程度を目安としています。
倍率方式は、主に郊外や農村部など、路線価が定められていない地域にある土地の評価に用いられ、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
これらの評価方法は、いずれも実勢価格よりも低く評価される傾向があるため、土地を所有すると相続税対策になる理由の一つです。
また、建物の評価額は固定資産税評価額が基準となり、実勢価格の約70%程度になるのが一般的ですが、個別の物件によって異なります。
固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村(東京都23区においては都)が決定するもので、建築費の約5割~7割程度が目安と言われますが、構造や築年数により幅があります。
新築時をピークに経年劣化により評価額は下がっていくため、築年数の古い建物ほど実勢価格との差が大きくなる傾向があります。
相続税評価額は、この固定資産税評価額に、構造や用途に応じた一定の補正率をかけて計算されます。
例えば、現金1億円は、そのまま額面通り1億円が相続税の評価対象です。
一方、1億円で不動産を購入した場合、評価額を約7,700万円(例:土地5,600万円、建物2,100万円)まで抑えられる可能性があります。
このように、現金の代わりに不動産で保有すると、大幅な評価減が期待できます。
不動産を賃貸に出すと、さらに評価額を抑えられます。
賃貸用不動産は「貸家建付地」として評価されるため、通常の土地より評価額が低く設定されます。
具体的には、所有地に賃貸物件を建てた場合、土地の評価額は自用地としての評価額から、借地権割合、借家権割合、賃貸割合を一定の計算式を用いて差し引くことで減額されます。
計算式は「自用地評価額 × (1 – 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」です。
借地権割合は地域ごとに国税庁が定めており、借家権割合は全国一律で70%、賃貸割合は実際に建物が賃貸されている割合です。
さらに、建物に関しても「貸家」として評価され、固定資産税評価額から借家割合(通常70%)を考慮して評価額が計算されます。
例えば、固定資産税評価額3,000万円の建物を全て賃貸に出しており、賃貸割合が100%の場合、建物の評価額は3,000万円 × (1 – 70% × 100%) = 3,000万円 × 30% = 900万円です。
これにより、賃貸物件を所有すると、単なる不動産保有に比べて、より大きな節税効果を期待できます。
相続税対策で特に活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度は、一定の条件を満たす相続人が土地を引き継ぐ場合に、その土地の評価額を大幅に減額できるものです。
この特例にはいくつかの種類があり、それぞれ適用できる対象者、減額される面積の上限、減額割合が異なります。
例えば、被相続人の居住用に使われていた宅地等(特定居住用宅地等)を一定の相続人が相続する場合、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
事業用に使われていた宅地等(特定事業用宅地等)を一定の相続人が相続する場合、400㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
そして、賃貸業などの貸付事業用に使われていた宅地等(貸付事業用宅地等)を一定の相続人が相続する場合、200㎡までの部分に対し評価額が50%減額されます。
不動産投資による相続税対策で主に活用されるのは、この貸付事業用宅地等の特例です。
ただし、条件を満たす必要があるため、制度の詳細や適用範囲については事前に専門家に確認することが大切です。
このように、不動産投資による相続税対策は、物件の活用方法や購入の方法次第で、非常に効果的な節税効果を生み出せます。
不動産投資を活用した相続税対策の仕組みについて見ていきましょう。
不動産投資による相続税対策では、土地の評価額圧縮効果が大きなメリットです。
不動産の土地は、相続税の評価額が市場価格(実勢価格)よりも低く計算されるため、現金より有利に相続税対策を進められるのが特徴です。
特に賃貸用不動産の場合、土地は「貸家建付地」として評価され、さらに評価額が圧縮されます。
貸家建付地の評価は、借地権割合と借家割合を考慮して減額されます。
そのため、同じ土地でも賃貸物件を建てて貸し出すと、相続税対策において大幅な節税効果が期待できます。
例えば、自用地評価額が1億円の土地に借地権割合60%の地域で賃貸物件を建て、全て賃貸(賃貸割合100%)した場合、貸家建付地としての評価額は1億円 × (1 – 60% × 70% × 100%) = 1億円 × (1 – 0.42) = 1億円 × 0.58 = 5,800万円です。
これにより、土地の評価額を4,200万円も圧縮できます。
この仕組みを活用すると、より評価額を抑える方法として有効です。
特に借地権割合が高い地域では、貸家建付地評価減の効果が大きくなります。
不動産投資を活用した相続税対策では、建物の評価額についても圧縮効果があります。
建物の評価額は通常、固定資産税評価額に基づいて計算され、これは実勢価格の約70%程度です。
さらに、賃貸用不動産として活用すると、「貸家」として評価され、借家人の権利分を考慮した減額が適用されます。
例えば、建物の固定資産税評価額が3,000万円であれば、借家権割合を差し引いた評価額が算出されるため、最終的な相続税評価額はさらに低くなります。
これにより、現金ではそのまま評価されてしまう相続財産を、不動産に置き換えると大きな節税が可能になります。
不動産投資による相続税対策では、金融機関からの借入金を活用することで評価をさらに下げられます。
相続税の計算では、被相続人のプラスの財産(資産)からマイナスの財産(負債)を差し引いた純資産に対して税金が課されます。
不動産の購入にあたって借入金を利用すると、その負債分が相続財産から差し引かれます。
これにより、実質的な相続税の課税対象額を圧縮できます。
例えば、1億円の不動産を購入する際に7,000万円の借入金を利用した場合、その借入金額が相続財産から控除されます。
結果的に相続税の課税額を大幅に減らせます。
ただし、無理な借入金の利用は返済リスクを高めるため、資金計画を慎重に立てることが大切です。
これらの方法を組み合わせ、不動産投資を適切に活用すると、相続税対策を効果的に進められます。
そして、専門家のアドバイスを受けながら進めると、より確実な対策が図れます。
相続税対策に効果的な不動産投資の種類は、以下の通りです。
アパートやマンションを一棟ごと購入する投資は、相続税対策として効果的な方法の一つです。
一棟投資では、建物全体や敷地を含めて賃貸用不動産として運用するため、貸家建付地として土地の評価額が圧縮されます。
建物自体の評価額が市場価格よりも低く算定されるため、相続税を節税する効果が期待できます。
さらに、一棟投資では複数の部屋を賃貸に出せるため、空室リスクを分散できる点もメリットです。
また、事業として不動産貸付業を行っていると認められれば、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等の適用を受け、土地の評価額をさらに50%(200㎡まで)減額できる可能性もあります。
区分マンション投資は、マンションの一室を購入して賃貸運用する方法です。
この投資手法は初期投資額が一棟購入に比べて低いため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。
相続税対策としては、賃貸中の物件であれば貸家評価減の適用により評価額が下がるため、節税効果を得られる場合があります。
ただし、土地や建物の管理費用が一棟や区分マンションと異なるため、維持管理に関する計画が大切です。
戸建ての住宅を購入して賃貸に出す投資方法も相続税対策として効果が期待できます。
特に地方や郊外エリアでは、土地付き戸建ての評価額が比較的低く抑えられることが多いため、相続時の負担も軽減される可能性があります。
また、ファミリー層をターゲットとした賃貸需要が見込めるため、安定した収益が得やすい点も魅力的です。
ただし、土地や建物の管理費用が一棟や区分マンションと異なるため、維持管理に関する計画が重要です。
タワーマンションへの投資も相続税対策の一手段として注目されてきましたが、近年の税制改正により、相続税評価額の計算方法が見直されました。
特に高層階の物件は、実勢価格と評価額の乖離が大きかったため、階層や築年数に応じた補正が加わることになり、以前のような大幅な評価圧縮効果は期待しにくくなっています。
ただし、立地条件が良いことが多く資産価値の維持や上昇が期待できるため、将来的な売却益も狙いやすい点がメリットです。
また、管理費や修繕積立金が高額になる場合があるため、収支計画には注意が必要です。
自分が所有する土地を活用し、賃貸アパートやマンションを建設する方法は、相続税対策として高い効果が期待できます。
この方法では、土地が貸付事業用宅地等とみなされると評価額が下がります。
また、建物の評価額も実勢価格より低く算定されるため、相続税を抑えられる可能性が高いです。
さらに、貸付事業用小規模宅地等の特例が適用される場合、土地評価額が大幅に圧縮されます。
ただし、初期費用や借入金の返済計画が重要なため、入念な資金計画のもとで進めることが必要です。
不動産投資を活用した相続税対策のメリットについて解説していきます。
不動産投資を行うと、相続税対策だけでなく、安定した家賃収入を得られる可能性があります。
賃貸用として物件を活用することで、毎月の収益を確保しつつ長期的な資産運用が可能です。
特に人口が集中する都市部や需要の高い地域の物件を選ぶことで、空室リスクを抑えつつ収益を安定化させられます。
不動産はその立地や市場環境によって、将来的に資産価値が上昇する可能性があります。
地価が上がるエリアや再開発が進む地域の物件を購入することで、相続税評価額を抑えつつ、不動産の市場価格が上がる恩恵を受けられるかもしれません。
適切な物件選びは、将来の資産形成に大きく影響します。
税理士だけでなく、不動産市場に詳しい専門家(不動産業者や不動産鑑定士など)に相談し、将来性のある物件を選定することが大切です。
不動産投資をする際に住宅ローンを利用する場合、多くは団体信用生命保険にも加入します。
この保険は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金によってローン残高が完済される仕組みです。
万が一のことがあった際にローンが完済される仕組みがあるため、残された家族に経済的な負担を残さずにすみます。
被相続人が多額の借入金を抱えたまま死亡した場合、その借入金も相続の対象となり、相続人は返済義務を負います。
しかし、団体信用生命保険に加入していれば、保険金によってローン残高がゼロになるため、相続人は借入金の返済負担から解放されます。
そのため、不動産投資は生命保険の代わりのような役割を果たし、相続税対策の一環となります。
インフレが進行した場合、現金の価値は目減りするリスクがあります。
一方、不動産はインフレに強い資産とされています。
不動産の実勢価格や家賃収入は物価上昇の影響を受けるため、インフレ局面で資産価値を保持しやすい特徴があります。
これにより、不動産投資は相続税対策と同時にインフレへのリスクヘッジとしても効果を発揮します。
相続税対策の一環として不動産を活用するメリットの一つに、小規模宅地等の特例があります。
この特例を活用することで、一定条件を満たした物件の土地の評価額が最大で80%減額されることがあります。
適用できる特例の種類や減額割合、面積上限は、その土地の利用状況によって異なります。
たとえば、賃貸用不動産であれば「貸付事業用宅地等」の要件に該当する場合があります。
こうした特例を適切に活用するためにも、事前に専門家のアドバイスを得ることが大切です。
不動産投資を活用した相続税対策のデメリットは、以下の通りです。
不動産投資では、購入した物件が空室になる可能性があり、家賃収入が得られなくなるリスクがあります。
特に立地や需要を十分に考慮せず物件を購入した場合、借り手が見つからないこともあります。
また、賃料相場が下落すると家賃収入も減少するため、購入時に想定していた収益が得られない可能性があります。
不動産投資を相続税対策として活用する際には、このような収益面のリスクも十分に検討する必要があります。
不動産市場は景気や地域の需要に大きく左右され、物件価格が下落するおそれがあります。
購入時に高額で取引された不動産が、将来的に価値を下げることも珍しくありません。
物件価格が大幅に下がると、売却時に十分な現金を得られない可能性があるため、相続税対策を目的とした投資でも注意が必要です。
不動産を保有している限り、修繕費や管理費といったランニングコストが発生します。
例えば、建物の老朽化が進むと修繕費が増加し、想定以上のコスト負担が発生することがあります。
また、管理会社へ委託している場合、その費用も継続的に発生します。
このようなコストは相続税対策の目的で購入した物件にも影響を与えるため、事前にしっかりと計画を立てる必要があります。
不動産投資を行う際、多くの場合融資を利用しますが、ローンの借り入れがある場合、金利の上昇リスクを考慮しなければなりません。
金利が上昇すると、毎月の返済額が増加し、収益性が低下する可能性があります。
特に変動金利型の融資を選択している場合、予期しない支出増加に直面することがあるため注意が必要です。
不動産は流動性が低い資産であり、必要な時にすぐに現金化するのが難しい場合があります。
市場環境や物件の条件によっては、売却まで時間がかかることもあります。
そのため、急遽現金が必要になった場合に対応しにくいというデメリットがあります。
相続税対策として不動産を活用する時も、このような流動性の低さを考慮することが大切です。
不動産を購入すると、不動産取得税や固定資産税などの税金が発生します。
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ発生する地方税です。
税率は原則として固定資産税評価額の4%ですが、宅地や住宅など軽減措置が適用される場合があります。
固定資産税は、土地や建物を所有している限り、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。
税率は原則として固定資産税評価額の1.4%ですが、市町村によって異なります。
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物に対して課される税金で、税率は原則として固定資産税評価額の0.3%ですが、市町村によって異なります。
これらの税金は相続税対策での不動産投資にも影響を与え、運用費用全体を増加させます。
このような税負担をあらかじめ把握し、資金計画に組み込むことが大切です。
不動産投資を活用した相続税対策でよくある失敗例について見ていきましょう。
不動産投資で相続税対策を考える際、節税効果にばかり注目し、収益性を十分に考慮せずに物件を購入してしまうケースがあります。
確かに、不動産を所有することで相続税評価額を下げる効果は期待できますが、家賃収入が見込めない物件や維持管理コストが高い物件を選ぶと、長期的には経済的な負担が大きくなりかねません。
物件を購入する際には、「節税効果」と「収益性」のバランスをしっかりと見極めることが大切です。
相続税対策として不動産投資を進める場合、家族の状況や将来のライフプランを考慮することが欠かせません。
例えば、物件の運用に継続的な手間がかかる場合や、家賃収入を家族でどのように分割するのかがあいまいな場合、相続後のトラブルの原因になりかねません。
特に共同相続人がいる場合は、共有名義のデメリットや物件管理を誰が行うのかといった具体的な内容を事前に話し合っておくことが大切です。
不動産は現金と異なり簡単に分割するのが難しい資産です。
そのため、相続発生時に遺産分割協議が難航し、不動産の売却で揉めてしまうケースもあります。
特に売却時の市場価格が購入時より下がっている場合や、「もっと有利な条件で売りたい」と考える相続人がいる場合は、調整がさらに困難になります。
不動産投資を相続税対策として利用する際は、売却の際のスムーズな対応や共有名義にしない工夫、家族間での十分な合意形成が必要です。
不動産投資による相続税対策の進め方は、以下のステップで進めましょう。
不動産投資を活用して相続税対策を進めるには、まず自分の財産状況や将来かかる可能性のある相続税額を正確に把握することが大切です。
現金や預貯金、不動産などの資産の種類や額、負債額などをリストアップし、税理士などの専門家に相談することで、具体的な相続税額や必要な対策を明確にできます。
このステップを怠ると、適切な対策を実施することが難しくなるため、慎重に進めましょう。
現状を把握した後は、具体的な相続税対策の目標を設定します。
例えば、相続税額をどの程度軽減したいのか、不動産からの家賃収入をどれだけ重視するのかを明確にすることがポイントです。
また、不動産投資が自分に適しているかどうかも検討する必要があります。
不動産投資は初期投資が大きく、長期的な運用が求められるため、自身の財務状況やライフプランに合っているかを判断してください。
不動産投資を活用した相続税対策を進める上で、信頼できる税理士や不動産業者を見つけることが非常に大切です。
税理士は相続税や不動産の評価額に詳しく、適切な助言を提供してもらえる専門家です。
不動産業者は、収益性が高く、相続税評価額を抑えるのに適した物件の選定をサポートしてもらえます。
評判や実績を調べ、慎重に選びましょう。
不動産投資では、物件選びが非常に重要です。
相続税対策の観点だけでなく、収益性や立地条件、将来的な資産価値にも配慮して選定する必要があります。
複数の物件情報を収集し、路線価や固定資産税評価額、物件の潜在的な利回りなどを比較検討してください。
また、物件によっては小規模宅地等の特例が適用される場合があるため、その点も確認しましょう。
物件が決定したら、資金計画を作成します。
自己資金の割合やローンの借入額と返済プランを明確にすることで、無理のない投資を実現できます。
不動産購入にあたり、金融機関からの融資を活用するケースが多いため、ローン審査を行い、適切な条件で融資を受けられるよう準備しましょう。
借入金を活用することで、相続税の負担軽減に役立つ場合もあります。
資金計画とローンの手続きを終えたら、物件の購入契約を締結し、引き渡しを受けます。
購入時には、不動産取得税や登記費用などの諸費用が発生するため、これも資金計画に組み入れる必要があります。
正式な契約を結ぶ際には、契約内容や費用をもう一度確認し、トラブルを防止するよう注意しましょう。
物件の引き渡し後は、賃貸募集を行い、運用を開始します。
家賃が安定的に得られるかどうかは、物件選びや管理の適切さが大切です。
また、確定申告で不動産所得を適切に計上することも大切です。
不動産投資を通じて得られる家賃収入が、相続税対策としての大きなメリットとなるため、継続的な運用の見直しや改善を行いましょう。
不動産投資は、相続税対策として非常に有効な手段の一つです。
不動産は現金や預金よりも相続税評価額が低くなるため、物件を購入することで相続税額を圧縮できる可能性があります。
また、賃貸用不動産の場合、「貸家建付地」として評価額がさらに低くなるほか、小規模宅地等の特例を活用することでさらに評価額を減額することも可能です。
安定的な賃料収入を得られる点や、インフレ対策にもなるといったメリットも不動産投資の魅力です。
一方、不動産投資には空室リスクや物件価格の下落、修繕費や管理費が発生するといったデメリットもあります。
必要なタイミングで現金化が難しいケースや、ローン金利の上昇がリスクとなる場合もあります。
そのため、相続税対策を目的とした不動産投資を始める際は、物件の評価や適切な資金計画、収益性や家族状況を十分に考慮し、信頼できる税理士や不動産業者のサポートを受けることが大切です。
不動産投資を活用した相続税対策は慎重な計画と運用によって大きな効果を発揮しますが、無計画に進めると失敗のリスクもあります。
適切な知識と専門家のアドバイスをもとに、効率的な相続税対策を行いましょう。
本記事が参考になれば幸いです。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。