
投資基礎知識



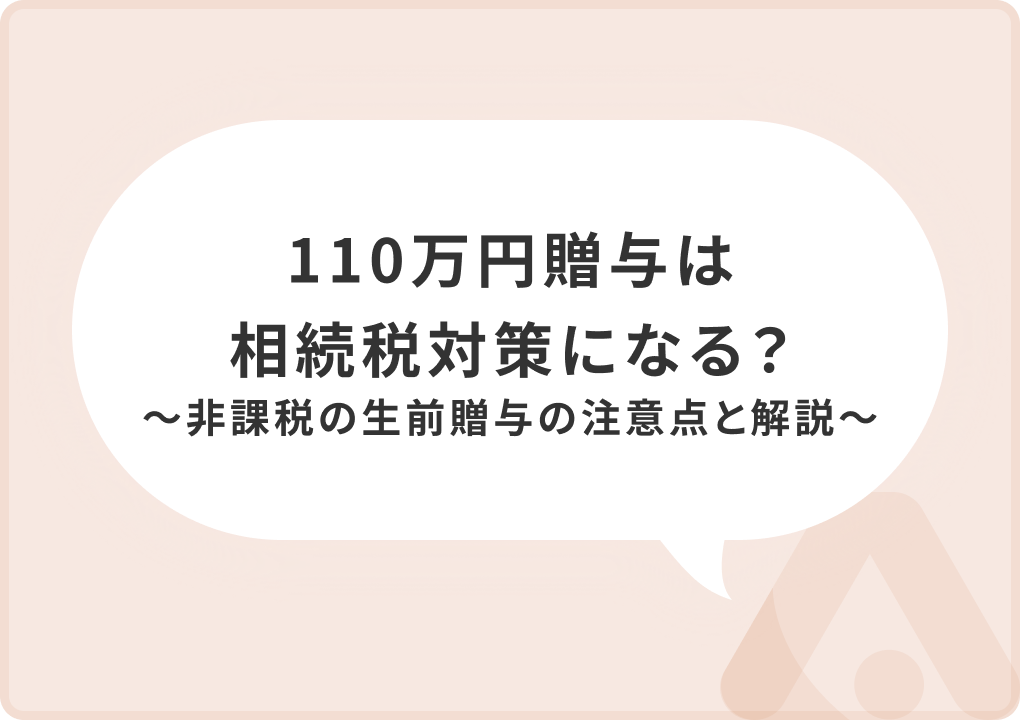
今からできる相続税対策として「生前贈与」は非常に有効です。特に110万円以内の年間贈与は、贈与税がかからない基礎控除を利用する方法として注目されています。しかし、税の制度には複雑な条件があり、内容を理解していないと相続税に影響を及ぼすリスクがあります。この記事では、相続税対策でよく聞く「110万円」の内容や注意点についてわかりやすく解説します。
目次
相続税対策を検討する際、「年間110万円までなら非課税で贈与できる」という話を耳にすることが多いですが、どんな仕組みかご存じでしょうか。
相続税とは、被相続人が亡くなった際に相続人に引き継がれる財産に対して課される税金です。
課税される財産には、現金、預金、不動産、株式、生命保険の死亡保険金等が含まれます。
一方、墓地の購入費や国や地方公共団体への寄付は非課税です。
相続税の額は、取得した財産額から基礎控除を差し引いた課税対象額に税率を適用して算出されます。
基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
この基礎控除内に収まる場合は相続税はかかりませんが、それを超えると課税対象となります。
課税対象額に対する相続税率は、10%から最高55%までの累進課税です。
生前贈与を活用すれば、被相続人が亡くなった時点の財産額を減らし、相続税を軽減できるため、相続税対策として有効です。
特に、贈与税の非課税枠を活用した生前贈与は、贈与税の負担を抑えつつ財産を移転できる有効な手段の一つです。
暦年課税は贈与税を計算する際の基本的な制度で、年間110万円までの贈与は非課税です。
この「暦年」とは、1月1日から12月31日までの1年間を指します。
この非課税枠を「基礎控除」と呼びます。
基礎控除額の110万円は、贈与を受ける人(受贈者)ごとに計算されます。
つまり、1人の受贈者が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
基礎控除額の110万円を超える部分については贈与税が課されますが、その課税率は対象額に応じて10%から55%までの累進税率が適用されます。
例えば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、150万円から非課税枠の110万円を差し引いた40万円が課税対象となります。
この40万円に対して贈与税率が適用され、贈与税額が計算されます。
生前贈与で暦年課税の非課税枠を毎年利用すると、長期間にわたり財産を分割して移転でき、贈与税負担を抑えつつ相続税対策を効率的に進められるメリットがあります。
年間110万円を継続的に贈与することで、将来の相続財産を減らす効果が期待できます。
ただし、同額を毎年贈与する場合は「定期贈与」とみなされると非課税にならない可能性があります。
「定期贈与」と判断されると、複数年分の贈与が一括で行われたものとみなされ、多額の贈与税が課税されるリスクがあります。
これを避けるためには、毎年贈与契約書を作成する等の対策が有効です。
暦年課税制度における贈与税の年間110万円非課税枠は、生前贈与を活用した相続税対策の基本となる仕組みです。
この仕組みについて、詳しく見ていきましょう。
生前贈与で、贈与税が非課税となる年間110万円の基礎控除は、贈与税法で定められた金額です。
この基礎控除は、すべての個人が利用でき、贈与者ごとに適用されます。
相続税対策を行う際には、この受贈者ごとの基礎控除を活用すれば、大きな節税効果が期待できます。
例えば、子どもが複数人いる場合、それぞれの子どもに年間110万円までの贈与を行うことで、家族全体でより多くの財産を非課税で移転させることが可能になります。
年間で110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。
つまり、1年間の贈与額が110万円以下であれば、税務署に贈与税の申告書を提出する必要がありません。
この非課税枠を活用すれば、財産を税金負担なく受け取れます。
たとえば、毎年110万円ずつ生前贈与を行えば、相続財産を徐々に減らし、結果として相続税対策につながります。
ただし、贈与の方法には注意が必要で、不適切に実施すると税務署に課税対象とみなされる可能性もあります。
110万円の非課税枠は、贈与を受ける人ごとに適用されます。
つまり、複数の人に贈与を行った場合、それぞれの受贈者に対して個別に110万円の非課税枠が使えます。
たとえば、子ども二人にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、合計220万円が非課税になります。
孫がいる場合も同様に、それぞれに110万円まで贈与することが可能です。
この仕組みを活用すれば、効率的に多くの財産を税金負担のない形で渡すことが可能です。
受贈者が未成年の場合や管理が必要な場合は、実際の運用に注意が必要です。
贈与は一度実行すると取り消すことが難しいため、受贈者の状況を十分に考慮した上で計画を立てることが重要です。
ここからは、年間110万円の贈与による相続税対策のメリットについて解説していきます。
年間110万円までの贈与は非課税とされており、この非課税枠を活用し長期的に生前贈与を進めていくことで、大きな節税効果が期待できます。
この方法は、毎年少しずつ財産を移転することで、相続時に課税対象となる財産の総額を減らし、結果として相続税を軽減する仕組みです。
例えば、年間110万円を10年間贈与すれば、合計で1100万円もの財産を税金負担なく移転できます。
これは、生前贈与を計画的に行うことで得られる相続税対策の重要なポイントです。
生前贈与をする際には、贈与する財産を現金に限らず自由に選べます。
不動産や株式、貴金属等も贈与の対象にできるため、自分の財産状況や受贈者の希望に応じた柔軟な対応が可能です。
特に、不動産を活用した評価額の低減等の工夫で、更なる相続税対策につなげることも期待できます。
贈与する財産を自由に選べる点は、贈与税や相続税の負担を最小限に抑える上で非常に大きなメリットです。
年間110万円までの非課税の生前贈与を行うことで、受贈者となる子や孫等が贈与された財産を自由に使えるようになります。
受贈者が必要とする学費や住宅購入費、生活費等に無理なく活用できるため、贈与する財産が有効に役立てられるのが特徴です。
また、家族間での財産移転が円滑に進むことで、高齢世代から若年世代への資産継承が進み、家計全体の資金管理を効率化する効果も期待できます。
ここからは、年間110万円の贈与による相続税対策のデメリットについて解説していきます。
年間110万円の非課税枠を利用した贈与は、相続税対策として非常に有効です。
しかし、毎年同じ金額を継続的に贈与している場合、それが「定期贈与」とみなされるリスクがあります。
「定期贈与」とは、贈与契約が毎年ではなく、一括して複数年分の贈与を行う意思で締結されていると税務署に判断されるケースです。
この場合、全額が一括で贈与されたものとして課税され、贈与税の非課税枠である110万円が適用されない可能性があります。
そのため、年間110万円を非課税で贈与するには、毎年その都度贈与することが大切です。
贈与税の非課税枠を利用して贈与した場合でも、贈与された財産が実態として受贈者のものでないと判断されると、「名義預金」と見なされる可能性があります。
たとえば、贈与者が受贈者名義の銀行口座に振り込んだお金を実質的に自分で管理している場合や、受贈者が贈与されたお金を自由に使えない場合は名義預金と見なされるリスクが高まります。
この場合、その財産は贈与とは認められず、相続財産として相続税の対象となる可能性があります。
贈与をする際には、受贈者自身が預金通帳と印鑑を管理し、実際に財産を自由に使用できるようにしておくことが大切です。
生前贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立しますが、贈与者の認知能力が低下すると、贈与契約の締結が難しくなる可能性があります。
特に、高齢になってから生前贈与を開始した場合、数年後には契約行為そのものができなくなるおそれがあるため、継続的な非課税贈与が困難になることがあります。
このリスクを避けるには、早めに計画を立てることが大切です。
加えて、贈与契約書を毎年作成し、贈与の実績をしっかりと残しておくことで、後々のトラブルを防げます。
近年の税制改正では、相続税と贈与税の「110万円」に関わる制度にも重要な変更がありました。
令和5年度の税制改正では、生前贈与や相続税に関連する制度が変更されました。
その中で特に注目されるのが、相続直前の贈与が相続財産として加算される期間の延長です。
具体的には、相続税の計算では、相続開始前の生前贈与額が従来の「相続開始前3年」ではなく、「最長7年」に延長されました。この改正により、贈与税の非課税枠を利用した生前贈与は、より相続税対策として慎重に計画する必要が生じています。
相続税と贈与税が一体課税化されつつある背景には、生前贈与を相続税回避の手段として利用するケースが増えていることがあります。
この改正によって、生前贈与が相続財産に加算される期間が延長されたため、計画的かつ長期的に110万円の非課税枠を活用することが一層重要です。
もう一つの重要な改正として、相続時精算課税制度の仕組みに「年間110万円基礎控除」が追加されました。
この制度は、相続時精算課税を利用しながらも、年間110万円までは非課税で贈与できるようにしたものです。
従来の相続時精算課税制度では、贈与額に対して一律で税額が計算され、非課税枠がありませんでした。
しかし今回の改正により、年間110万円までの基礎控除を適用できます。
この改正は、贈与税が発生しない範囲を拡大し、生前贈与をより柔軟にできるようにする目的で導入されました。
ただし、相続時精算課税制度は、相続発生時に贈与財産が相続財産に加算される仕組みのため、相続税の計算に影響を与える可能性があります。
具体的な税額や対策については、その人の財産状況や家族構成に応じて異なるため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
令和5年度の税制改正で最も注目された変更点の一つが、暦年贈与の相続財産への持ち戻し(加算)期間の延長です。この改正について解説していきます。
2024年の税制改正により、相続税計算の際に生前贈与が相続税の対象に加算される期間が変更されました。
これまでは「3年間」とされていた加算期間が「最長7年間」に延長されます。
この改正により、例えば110万円の贈与を毎年行った場合、贈与開始から7年以内に相続が発生すると、その期間中の贈与額が相続財産に加算される可能性があるということです。
この延長措置は相続税の課税逃れを防止する目的から導入されています。
毎年非課税枠内での贈与を計画的に実施していても、相続時にこれらが計算上加算されることで相続税の負担が増える場合もあるため、事前にしっかりと贈与計画を立てることが大切です。
今回の税制改正で一部救済措置として導入されたのが、「延長された4年間の贈与額に関する控除」です。
具体的には、直近3年間を超える4年間分の贈与額については、年間100万円を上限に相続税の課税対象から控除される仕組みです。
この控除によって、非課税枠で贈与した財産の一部が相続財産に加算される影響を軽減できます。
例えば、贈与税の基礎控除である110万円を利用し、そのうち100万円が控除対象として認められた場合、実際に課税対象となる贈与財産の金額は大きく抑えられます。
この制度は、相続対策として生前贈与を活用する際に柔軟性を提供するものですが、あくまで計画的な運用が求められます。
このように、税制改正を正しく理解し、相続税対策を進めるには制度の情報を把握するとともに、専門の税理士に相談しながら適切な贈与計画を立てることが大切です。
安全に110万円の贈与を行うための方法は、以下の通りです。
相続税対策として110万円の非課税枠を利用した贈与をする際には、贈与契約書を必ず作成・保管することが大切です。
贈与は、贈与者と受贈者が合意した財産の移転契約として成立しますが、口頭の約束だけでは後にトラブルが発生する可能性があります。
そのため、文書で贈与契約書を作成し、日付や贈与した財産の内容、金額を明確化しておきましょう。
また、契約書があれば、税務署から贈与が「定期贈与」と判断されるリスクを減らせます。
適切に記録を残すことで、将来的な課税トラブルも防げます。
贈与を行う際には、現金の手渡しではなく、銀行振込を利用するのがおすすめです。
銀行振込を利用することにより、贈与の事実が明確な記録として残り、後に税務署から指摘を受けた際にも贈与が正しく行われたことを証明する材料となります。
また、振込の際には「贈与」という名目を明記することで、用途が明確になり、相続税や贈与税の課税対象でないことを示しやすくなります。
これらの手順を徹底することで、安全かつ正確な生前贈与を実施できます。
110万円の贈与を安全に行うには、受贈者自身が通帳と印鑑を管理することも大切です。
贈与は、実際に財産が受渡しされたという実績が認められることが基本です。
しかし、実際には贈与者が管理している名義預金と判断されるケースがあります。
これを避けるため、受贈者が自身の通帳と印鑑を保有し、銀行の入出金を管理する仕組みを確立する必要があります。
また、受贈者自身が財産を自由に使用していることを示すことで、適切な贈与だと判断されやすくなります。
年間110万円の非課税枠を利用した贈与は、誰に対して行うことができるのでしょうか?
また、複数の人に贈与する場合や、贈与を受ける人(受贈者)に関して特に注意すべき点はあるのでしょうか。
相続税対策として年間110万円の非課税枠を利用した贈与をする場合、その対象者を慎重に選ぶことが大切です。
贈与を受ける対象として一般的なのは、子や孫(18歳以上)といった相続人に該当する人たちです。
これにより、相続時の財産を減らし、将来的な相続税を軽減する効果が期待できます。
また、子や孫以外にも、親族関係にない人や友人にも贈与できます。
ただし、相続税対策としては、法定相続人に贈与を行う方が効果的です。
また、贈与した財産が相続財産に加算される期間が改正により延長されているため、贈与計画は早めに立てることをおすすめします。
年間110万円の贈与は受贈者ごとに適用されるため、複数人へ贈与する場合、それぞれの非課税枠を適切に活用することで、効率的な相続税対策を図れます。
例えば、子供が2人いる場合、それぞれに110万円ずつ贈与すれば、合計220万円を非課税で移転できます。
ただし、注意すべき点は、同じ金額を継続的に贈与することで、それが「定期贈与」とみなされてしまうリスクがあることです。
定期贈与と判断されると、一括で贈与税が課税される可能性があります。
このような問題を避けるためにも、贈与契約書を作成し、毎年内容を見直すことが推奨されます。
また、贈与する際は、受贈者が適切に財産を管理できるかどうかも考慮が必要です。
特に金銭を贈与する場合、その使途を受贈者が自由に決定できることが原則で、贈与者が利用を強制すると、税務上問題視される場合があります。
年間110万円贈与以外の代表的な相続税対策をいくつかご紹介します。
不動産は相続財産の中でも評価方法が特殊で、活用次第で相続税対策に有効です。
不動産を所有している場合、評価額が時価に比べて低くなるケースが多いです。
特に賃貸物件を所有したり、土地を分割活用したりすることで、評価額を引き下げられる可能性があります。
相続税額の計算では、土地の評価が「路線価」や「固定資産税評価額」を基準として行われるため、実際の市場価格よりも低めに見積もられることが一般的です。
また、土地を活用してアパートやマンションを建設することで、貸家建付地の評価減が適用され、さらに税負担が軽減することがあります。
このような方法は、相続税対策を考える際に有効な手段のひとつです。
生命保険を活用することも相続税対策として非常に効果的です。
生命保険金については、一定の非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、非課税枠は1,500万円で、この額までの保険金に相続税は課されません。
ただし、保険金を受け取る際に「誰が契約者で誰が受取人か」によって課税対象が異なるため、契約の際には慎重に検討する必要があります。
生命保険は、現金で直接相続財産を受け渡せる点も魅力の一つです。
養子縁組も相続税対策のひとつです。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
そのため、法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も多くなり、結果として課税される財産が減少します。
ただし、養子縁組には一定の制限があります。
相続税の計算上は、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は最大2人までが法定相続人として認められます。
この範囲内で養子縁組を行うことで、合法的に相続税の負担を軽減できます。
ただし、節税目的での養子縁組にはトラブルやリスクが伴う場合があるため、慎重な判断と専門家への相談が必要です。
相続税対策として年間110万円の贈与を活用することは、多くの方が検討する節税手段の一つです。
しかし、この手法を効果的かつ安全に実施するには、税理士への相談が不可欠です。
相続税や贈与税は法律や制度が複雑で、無計画に進めることで課税対象となってしまったり、トラブルに発展する可能性もあります。
まず、贈与税の非課税枠である年間110万円を活用する場合でも、適切な贈与契約書を作成して贈与の事実を証明できるよう準備することが大切です。
また、定期贈与や名義預金と判断されることを防ぐには、財産の移動方法や管理について専門的なアドバイスを受ける必要があります。
これらは、税務署の指摘を避けるために欠かせない要素です。
さらに、相続税と贈与税を取り巻く税制改正が進められている近年では、その影響を正確に把握し、適切に対策を講じることが大切です。
特に、令和5年度の税制改正で導入された「相続前贈与加算」期間の延長や相続時精算課税制度における新たな基礎控除等、税制の変化は相続税の計算や対策に大きな影響を及ぼしています。
税理士への相談を通じて、贈与額やタイミング、家族間での財産分配の方法等、個々の状況に合わせた最適な相続税対策を計画できます。
また、専門知識を活用することで、将来的な税負担を軽減するだけでなく、手続きを円滑に進められます。
相続税対策や生前贈与を検討している方は、一度専門家に相談することをお勧めします。
年間110万円の贈与を活用した生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段です。
この方法を利用することで、相続税の負担を軽減し、財産を円滑に次世代へ引き継ぐことができます。
しかし、非課税枠を超えてしまう場合や、税法上のルールを守らない場合は、贈与税が課税されたり、相続税の加算対象とされたりすることもあります。
特に、定期贈与や名義預金とみなされないための適切な手続きや管理が重要です。
また、令和5年度の税制改正による相続前贈与加算期間の延長や、贈与税と相続税を統合的に考慮した改正点にも注意が必要です。
そのため、贈与を計画的に進める際には、税務知識を正しく理解し、信頼できる税理士や専門家に相談することを強くお勧めします。
相続税対策は、早めに取り組むことで効果を発揮します。
適切な計画のもと、110万円の非課税枠を有効に活用し、自分や家族にとって最適な財産管理を実現しましょう。
ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。