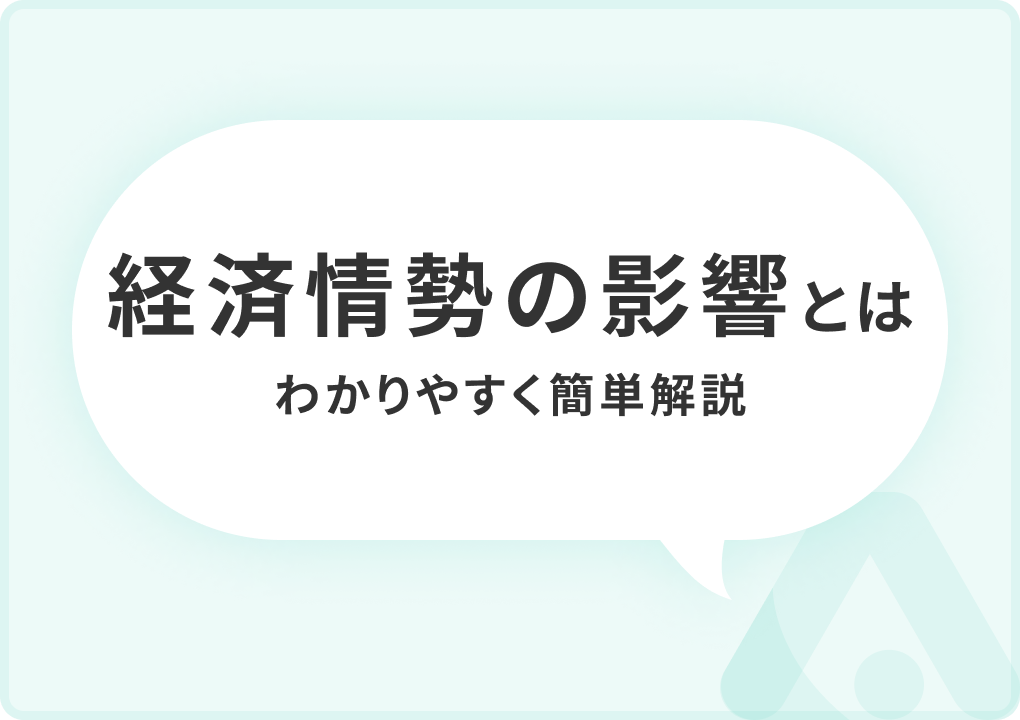
投資基礎知識



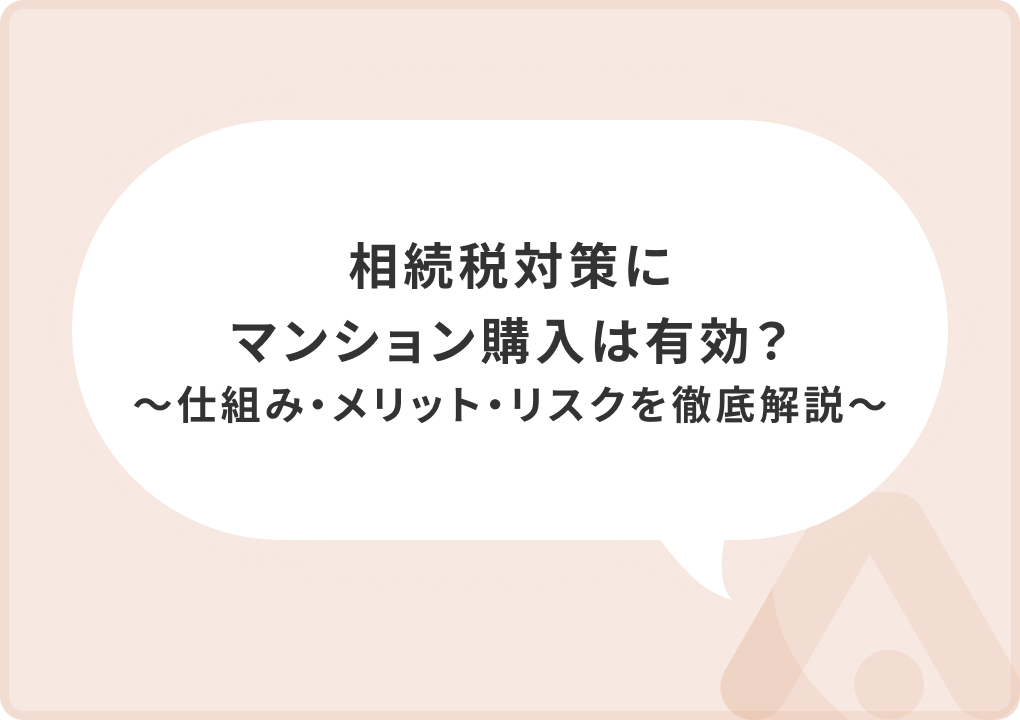
本記事では、相続税対策としてマンション購入が注目される理由を徹底解説。評価額の圧縮や債務控除、小規模宅地等の特例など節税の仕組みに加え、家賃収入・インフレ耐性・所得税の軽減など多角的なメリットについても紹介します。物件選びやリスク管理、専門家の活用法まで網羅した内容です。相続税対策にマンション購入を検討している方、ぜひ一読ください。
目次
マンション購入が相続税対策として注目される理由は、現金や預金に比べて「相続税評価額」を低く抑えられる点にあります。
現金はそのままの金額で評価される一方、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準にされるため、時価よりも安く見積もられる傾向があります。特に賃貸用としてマンションを保有すれば、貸家としての評価減や小規模宅地等の特例、ローンによる債務控除など複合的な節税策が活用可能です。これにより、同じ資産額でも実際の相続税額に大きな差が生まれます。
不動産を戦略的に組み込むことで、節税と資産形成の両立が期待できます。本記事では、相続税対策に関する内容を解説していきます。
相続税の計算において、現金と不動産では大きく評価方法が異なります。現金や預貯金は額面通り、つまり100万円なら100万円として評価されるのに対し、不動産は時価ではなく「相続税評価額」で算出されます。
これは、土地なら路線価、建物なら固定資産税評価額が基準となるため、実際の市場価格よりも2〜3割低くなることが一般的です。評価額が低ければ課税対象額も下がるため、結果として支払う相続税を軽減できるのです。
現金を不動産へと組み替えることで、自然と課税対象を抑える効果が見込めます。
所有している不動産が賃貸中であれば、相続税評価額はさらに圧縮される可能性があります。これは、貸家や貸付事業用宅地とみなされることで、一定の評価減が適用されるためです。
例えば、借家権割合や貸家建付地としての評価減によって、同じ物件でも自宅として所有する場合よりも相続税評価が2〜4割低く見積もられるケースもあります。実質的な資産価値は高いままでも、税法上の評価が下がることで節税につながります。
収益物件として運用しながら資産を引き継げる点が、賃貸マンション活用の大きな利点です。
相続税の大幅な圧縮を狙うなら、「小規模宅地等の特例」の活用は欠かせません。この制度を使えば、一定条件を満たす土地について、相続税評価額の最大80%までの減額が認められます。賃貸用不動産であれば、貸付事業用宅地として50%の評価減が適用可能です。これにより、本来なら数千万円の課税対象となる土地が、実質的に半額以下で評価されるケースもあります。
マンション投資はこの特例と相性が良く、事前に要件を整えておくことで、より効果的な相続税対策が実現できます。
マンション購入の際に金融機関からローンを組んでいる場合、その未返済分(負債)は相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」と呼び、課税対象額を減らすための有力な手段となります。
例えば、1億円の借入で購入した不動産があり、相続時に5,000万円のローン残高があれば、その5,000万円分が相続財産から控除される仕組みです。節税効果を意識した不動産取得では、ローン活用も立派な戦略のひとつです。ただし、名義や借入の目的に関する条件を満たす必要があるため、事前の計画設計が重要になります。
相続税の額は、同じ資産額でも「保有形態」によって大きく変わります。特に現金で相続するのか、それとも不動産として相続するのかによって、課税評価の基準が異なるのがポイントです。
現金はそのまま評価されるのに対し、不動産は路線価や固定資産評価額をもとに評価され、賃貸物件であればさらに低く算定される傾向があります。加えて、ローン残高の控除や小規模宅地等の特例が適用されるケースもあり、実質的な税負担が軽減される可能性が高まります。
ここでは、1億円という資産を例にとり、形態ごとの相続税額を比較しながら、その差と仕組みを詳しく見ていきます。
仮に1億円の現金をそのまま相続した場合、相続税評価額も1億円のままになります。
例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)なので、課税対象は6,400万円となります。相続税率は累進制で、税額は約1,200万円前後にのぼるケースも珍しくありません。現金は分割がしやすく、相続人間で揉めにくいという利点がある一方で、節税の観点では不利です。資産のすべてがそのまま課税対象となるため、事前の対策を講じないと相続税負担が大きくなりがちです。
早めに現金を他の資産へシフトする選択が求められます。
同じ1億円でも、現金を活用して賃貸用マンションを購入した場合、相続税評価額は大幅に圧縮される可能性があります。
建物部分は固定資産税評価額で、土地は路線価で評価され、時価の6〜7割程度に収まることが一般的です。さらに、他人に貸している物件であれば、借家権割合(30%程度)や貸家建付地評価の減額が適用され、総合的な評価額は5,000万円前後になるケースも。これにより、課税対象が大きく下がり、相続税も半分以下になる可能性があります。加えて、家賃収入も得られるため、節税と資産運用の両面で優れた手段といえるでしょう。
マンション購入時にローンを組むことで、相続税のさらなる節税が可能になります。なぜなら、未返済の借入金は相続財産から「債務控除」として差し引かれるからです。
例えば、1億円の物件をフルローンで購入し、相続時に8,000万円の残債があれば、その金額分が課税対象から除外されます。結果的に、不動産評価の圧縮と合わせて大幅な節税が実現可能です。ただし、実務上は返済能力や借入名義、使用目的などを明確にしておく必要があり、不適切な借入は税務署から否認されるリスクもあるため注意が必要です。
適切な設計と専門家の助言が節税成功のカギとなります。
マンション購入は相続税の節税手段として広く知られていますが、それに加えてさまざまな副次的メリットも兼ね備えています。単なる評価圧縮にとどまらず、収益性や資産防衛、所得控除といった多角的な利点が期待できるため、長期的な視点で見た資産形成にも大きく貢献します。
ここでは、相続対策におけるマンション購入の主なメリットを4つの観点から詳しく解説します。
賃貸マンションを所有すれば、相続税対策の効果だけでなく、継続的な家賃収入を得られるという経済的なメリットがあります。
相続発生前に家賃収入があれば、資産としての「活用度」が高くなり、税務上の評価額がさらに抑えられる可能性もあります。加えて、毎月のインカムゲインは老後の生活資金や他の相続人への資金分配の補助としても活用でき、資産運用の一環として魅力的です。特に立地条件や設備内容に優れた物件であれば、長期的な安定収入が見込めるため、単なる節税目的を超えた「利益を生む資産」としての役割も果たします。
現金や預貯金はインフレによって実質的な価値が目減りするリスクがありますが、不動産はその影響を受けにくい資産として位置づけられています。
特に都市部や人口が集中するエリアのマンションは、土地の希少性や需要の高さにより、長期的に資産価値を保ちやすい傾向があります。相続後に資産を維持・運用する上でも、インフレ耐性を持つ不動産はポートフォリオの安定化に貢献します。物価が上昇しても賃料や資産価値もそれに応じて上昇するため、インフレ環境下でも購買力を維持しやすい点が、不動産ならではの強みです。
賃貸マンションの運営には、管理費・修繕費・減価償却費といったさまざまな経費がかかりますが、これらは確定申告時に必要経費として計上可能です。そのため、不動産所得が赤字になった場合、給与所得など他の所得と損益通算することで、結果的に課税所得が減少し、所得税や住民税の節税につながることがあります。
また、節税の仕組みを正しく活用すれば、表面的には赤字でもキャッシュフローがプラスとなる「節税型不動産投資」も実現可能です。相続税だけでなく、年間の税負担軽減という観点でも、マンション購入は有効な戦略といえるでしょう。
マンション購入は、将来的な資金準備という点で生命保険のような役割を果たすこともあります。
一例を挙げると、団体信用生命保険付きのローンを活用すれば、万が一の際にローン残債が免除され、不動産そのものが無借金状態で遺族に引き継がれます。これは、死亡保険金のように遺族の生活保障や納税資金の補填に活用できるため、生命保険と同様の機能を果たします。さらに、現物資産として残るため、将来的に売却や賃貸により活用の幅が広がり、遺族の選択肢が多いという点でも有利です。
リスクヘッジと資産承継を同時に実現できる点が、大きな魅力です。
マンションの取得は相続税対策として有効ですが、節税効果だけに注目しすぎると、思わぬ落とし穴に陥ることもあります。不動産は流動性の低い資産であり、現金とは異なる管理負担やリスクが伴います。また、将来的な相続時には、遺産分割の難航や資金繰りの問題が表面化する可能性も。
この章では、マンションを活用した相続対策を実行する際に押さえておくべき4つの注意点を解説します。
マンションは資産価値が高く見込まれる一方、現金化に時間がかかるため、相続税の納付期限(原則10ヶ月以内)に間に合わないリスクがあります。特に、現金や預金の比率が少ない相続財産の場合、不動産を売却するか、別途資金を用意しなければ納税が難しくなります。賃貸物件であっても、即座に売却できるとは限らず、タイミング次第では不利な条件で手放すことにもなりかねません。
納税資金をどう確保するかという視点も、不動産購入時の重要な検討事項です。
賃貸用マンションは、所有しているだけで継続的に収益を生むというわけではありません。立地や建物の状態、需要の変化によっては空室が続くこともあり、家賃収入が安定しない可能性があります。さらに、築年数が経過すれば、設備の更新や大規模修繕が必要になり、思わぬ支出が発生するケースも。
節税目的で購入したつもりが、維持管理費や修繕費によって収支が悪化し、本末転倒となる恐れがあります。不動産は「持ち続ける責任」が伴う資産であることを忘れてはいけません。
現金と異なり、不動産は簡単に分割できないため、相続人間での公平な配分が難しく、遺産分割トラブルの原因になりがちです。
特に、1人の相続人が不動産を相続する場合、他の相続人には代償分割や代金の支払いが必要になるなど、金銭的な不均衡が生まれることがあります。また、事前に誰が所有するのかを決めていないと、遺言や協議内容をめぐって感情的な対立に発展することも。
不動産を残す場合は、相続後の分配方法まで視野に入れた計画が不可欠です。
マンション購入が相続税の圧縮に役立つのは事実ですが、過度な節税目的での投資は税務当局に否認されるリスクがあります。
特に、相続直前の不自然な不動産購入や、実態のない賃貸経営は「租税回避行為」とみなされ、想定していた控除や評価減が認められない可能性も。また、節税効果ばかりに目を向けて、収益性や市場価値を無視した物件を選んでしまうと、将来的に損失を抱える恐れもあります。
税制と投資判断のバランスをとることが、失敗しないための鍵です。
相続税の節税を目的としたマンション購入では、「どのような物件を選ぶか」が節税効果の大きさを左右します。評価額の圧縮度合い、収益性、管理の手間、相続後の分配しやすさなど、さまざまな観点から物件タイプを見極める必要があります。
節税に有利なマンションには傾向があり、その中でも特に注目されるのが「ワンルームタイプ」と「一棟買い」、そして「タワーマンション」といった形態です。
ここでは、それぞれの特性や最新の税制動向を踏まえた選び方をご紹介します。
ワンルームマンション
比較的少額から投資でき、都心部など賃貸ニーズの高いエリアでは安定した家賃収入が期待できます。分譲物件として管理も外部任せにできるため、手間がかかりにくい点も魅力です。
一棟マンション
土地と建物を丸ごと所有できるため、貸家建付地評価や減価償却の自由度が高く、相続税評価の圧縮余地が大きいのが特徴です。ただし、修繕・運営管理の負担が重くなるため、不動産運用にある程度の知識と時間を割ける方に向いています。
それぞれの特徴を理解し、目的や体力に応じた選択が節税成功のカギです。
かつてタワーマンションは、実勢価格に比べて相続税評価額が極端に低くなるという理由で、節税対策の代表格とされてきました。しかし、近年の税制改正により、階層による価値の差や不自然な節税行為への是正措置が導入され、従来のような効果は期待しにくくなっています。
特に2023年以降は、固定資産税や相続税評価において市場価格との乖離を是正する動きが強まっており、高層階住戸の節税効果は限定的です。ただし、立地や管理状態が良好な物件は資産価値の維持に優れており、節税よりも長期保有による資産防衛の視点で選ぶのが現代的な戦略といえます。
マンションを活用した相続税対策は、単に評価額を下げるだけでは成功とはいえません。大切なのは、節税効果を最大限にしながらも、相続人全体にとって負担の少ない「実用的な資産承継」を実現することです。物件選び、運用方針、納税資金の確保、将来の分割方法など、包括的に計画を立てておく必要があります。
この章では、対策の効果を持続させつつ、相続時のトラブル回避にもつながる2つの重要な視点について解説します。
マンションを購入して相続税の軽減を図る際には、被相続人の都合だけでなく、将来その資産を受け継ぐ相続人たちの人生設計にも目を向ける必要があります。
例えば、特定の相続人だけが不動産を取得すると、他の相続人との間で不平等感が生まれ、トラブルの火種になることも。また、家賃収入をどのように分配するのか、管理を誰が行うのかといった実務面も重要です。
不動産は長期にわたって影響を及ぼす資産であるため、相続人全体のライフプランや経済状況をふまえた上で、柔軟かつ公平な形で承継できる資産設計を行うことが、対策成功の鍵となります。
不動産を相続税対策として購入する場合、購入時の節税効果だけでなく、「その後どう扱うか」という出口戦略まで視野に入れた設計が不可欠です。
将来の売却を前提とするならば、流動性や需要の高いエリアを選ぶ必要があります。一方で、相続人がそのまま物件を保有・運営する可能性があるなら、収益性と管理のしやすさも重要な選定基準です。また、税務署による課税評価や将来の税制改正への対応も考慮しておく必要があります。
資産価値が維持できず売却困難な物件を抱えると、かえって負担になるケースもあるため、長期的な視点での判断が求められます。
マンションを活用した相続税対策は、税務知識だけでなく不動産評価や法的要件にも関わる複雑な分野です。節税のつもりで行った対策が、税務署に否認されたり、相続人間のトラブルにつながったりするリスクもあるため、事前に専門家の助言を受けることが非常に重要です。
税理士の中でも、相続税を専門とする実績豊富なプロであれば、評価減の最適な活用方法や申告時の注意点、将来を見据えた資産設計までトータルでサポートしてくれるためおすすめです。物件の選定や購入タイミングによって節税効果が大きく変わることもあるため、早めに相談をし、情報を得ることも成功への第一歩です。
マンション購入は、相続税の節税を実現するための有力な選択肢です。現金よりも低く評価される不動産の特性を活かし、貸家評価や債務控除、小規模宅地等の特例を活用することで、同じ資産額でも税負担を大きく軽減できます。さらに、家賃収入や所得税対策、生命保険の代替機能など、長期的な資産形成にも有利に働きます。
ただし、不動産は流動性が低く、管理や分割の難しさなどリスクも伴います。相続人全体のライフプランや売却・承継の出口戦略を見据えた投資判断が重要です。
確実な節税効果を得るためにも、早い段階で相続税に精通した専門家に相談し、計画的に対策を進めましょう。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。