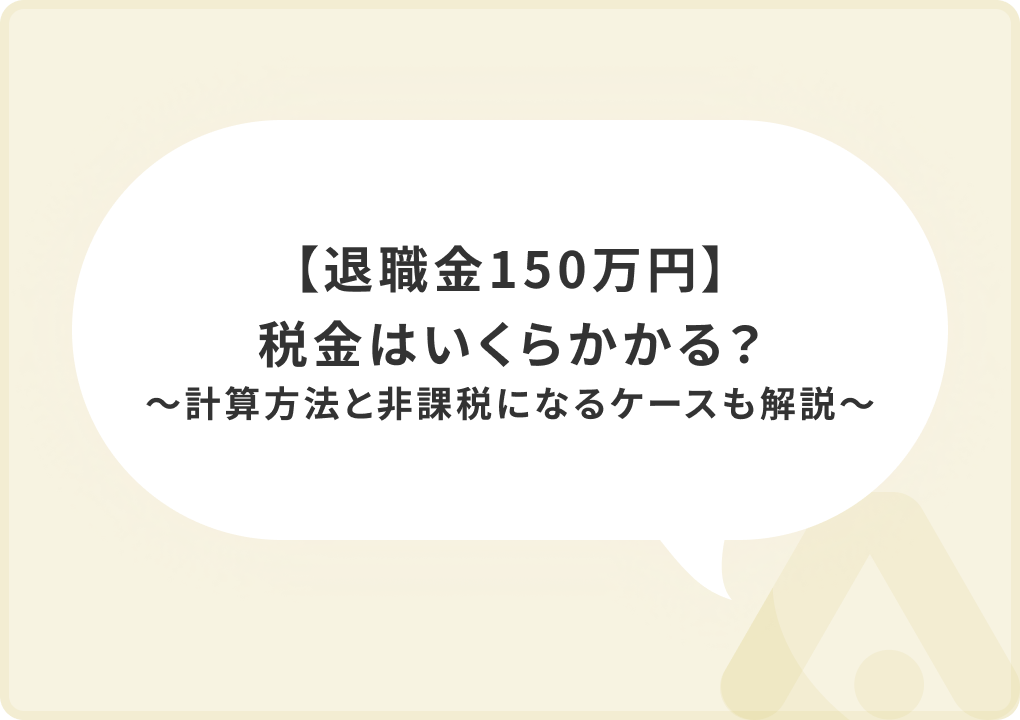
退職金運用



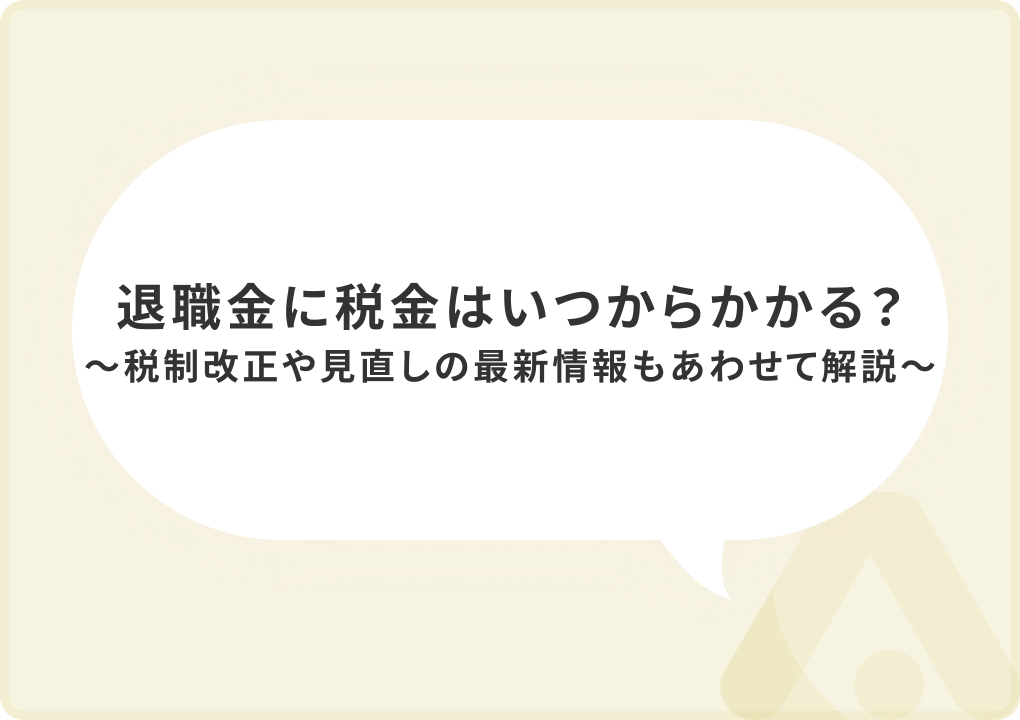
退職金にかかる税金は「いつ受け取るか」によって負担が変わります。政府による税制の見直しや、勤続年数による控除額の違いも押さえておきたい重要なポイントです。この記事では、退職金の課税タイミングや控除の仕組み、最新の税制改正情報、iDeCoや企業型DCの節税効果、確定申告が必要なケースなどをわかりやすく解説。損をしないための対策を具体的に紹介します。
目次
退職金に対する課税は、実際にお金を受け取ったタイミングで発生します。一般的に、会社を辞めた時点で「退職所得」として税金が関わってきますが、重要なのは「支払日」ベースで判断される点です。
つまり、退職日ではなく退職金の支給日が、税務上のスタートラインとなるのです。近年では、税制改正により短期勤続者への取り扱いが厳格化された背景もあり、いつ・どのように退職金を受け取るかが、将来的な税負担を左右するポイントになります。
退職金に課税される時期は、「実際にお金が支払われた日」が基準となります。これは、退職した日ではなく、企業側が退職金を従業員の口座に振り込んだタイミングを指します。
例えば、3月末で退職しても、退職金が4月に支払われれば、課税対象は翌年度の所得となります。この支給と課税のズレを正しく理解していないと、確定申告のタイミングや税額計算に誤りが生じる可能性があります。
年をまたいで退職金が支払われる場合は、課税年度が変わることで他の所得と合算される可能性もあり、結果的に税額が増えるケースもあるため注意が必要です。
国税庁の定めるルールでは、退職所得の「収入すべき時期」とは、退職金の支払日を指します。これは、実際にお金を手にした日が課税対象としての起点になるという考え方です。
退職金が確定していても、支払いが遅れるとその年の所得には含まれず、実際に受け取った年に所得としてカウントされます。例えば、3月末に退職して退職金が5月に振り込まれた場合、その退職金は5月の年分として扱われます。
このように、収入の計上タイミングは「支給日主義」に基づいているため、退職時期と支給時期がずれると、思わぬ税務上の影響が出ることもあります。
多くの場合、退職金には源泉徴収が行われており、確定申告をしなくても問題ありません。ただし、一定の条件に当てはまる場合は申告が必要になります。
例えば、退職時に「退職所得申告書」を提出していなかった場合、税率が一律で高く設定されるため、あとから申告することで税金の還付が受けられる可能性があります。また、年の途中で退職してほかの収入がある場合や、医療費控除・ふるさと納税など他の控除を併用したいときにも申告が有利です。
さらに、年金形式で退職金を受け取る場合は総合課税扱いとなるため、確定申告によって税額が調整されることがあります。
退職金に関する税制の変更は、適用開始時期が改正内容によって異なります。これらの改正により、退職金の受け取り方やタイミングが税負担に影響を及ぼす可能性があるため、最新の情報を確認し、適切な対策を講じることが重要です。
2022年1月1日から、勤続年数が5年以下の従業員が受け取る退職金に対する課税方法が変更されました。
従来、退職所得は退職所得控除後の金額を2分の1に軽減する措置が適用されていましたが、改正後は、控除後の金額が300万円を超える部分について、この軽減措置が適用されなくなりました。これにより、短期間で退職する場合の税負担が増加する可能性があります。
なお、役員等に対する退職金については、以前からこの軽減措置の適用外となっています。
令和7年度(2025年度)の税制改正では、退職所得控除の適用に関する見直しが検討されています。
具体的には、退職金や確定拠出年金の一時金を受け取る際、過去に他の退職手当等を受給している場合の勤続年数の重複期間を調整する期間が、従来の4年から9年に延長される予定です。
これにより、短期間で複数回の退職金等を受け取る場合の税負担が増加する可能性があります。最新の税制改正情報を把握し、適切な資産形成計画を立てることが重要です。
退職金に対する一律課税案は、勤続年数に関係なく同一の課税基準を適用することで、税負担の公平性を図るものです。これにより、長期間勤務した場合の税優遇が縮小される可能性があります。
また、短期退職手当等に関する改正では、勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の課税方法が見直され、一定額以上の部分について軽減措置が適用されなくなりました。これらの改正は、退職金の受け取り方やタイミングに影響を与えるため、事前に十分な計画と対策が必要です。
退職金は、他の給与所得とは異なる「退職所得」として特別な税制上の扱いが設けられており、一定の条件を満たせば課税対象額が大きく減る、または非課税になる場合もあります。
特に「退職所得控除」は大きなポイントで、長年勤務していた人ほど控除額が増える仕組みです。また、退職所得として認められるためには「退職所得申告書」の提出も重要です。これを出していないと高税率の源泉徴収がされてしまい、損をすることもあります。
さらに、確定拠出年金制度などを併用すれば節税メリットも期待できます。それぞれ見ていきましょう。
退職金の課税対象額を決めるうえで重要なのが「退職所得控除」です。控除額は勤続年数に応じて変動し、勤務期間が長いほど多く控除されます。
計算式は、勤続20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。この控除額を退職金から差し引いた上で、さらにその半分のみが課税対象となるため、他の所得と比べて税負担が大幅に軽減されます。
実際の控除額を事前にシミュレーションしておくと安心です。
退職金にかかる税額は、勤続年数が長いか短いかで大きく変わります。勤続年数が長いほど退職所得控除の金額が増えるため、課税対象が減り、実質的な税負担が軽くなる仕組みです。
一方で、勤続5年以下で退職した場合は、控除後の金額に対する2分の1課税が適用されない「短期退職手当等」とみなされ、税金が重くなる可能性があります。
したがって、退職時期の判断や計画的なキャリア設計が、手取り退職金額に直結する重要なポイントとなります。
退職金だけでなく、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型DC(企業型確定拠出年金)を上手に活用することで、退職時の税負担をさらに軽減できます。これらの制度は拠出時・運用時・受取時それぞれで税制優遇があるのが特徴です。
特に退職金として一時金で受け取る場合は、退職所得控除の対象となり、他の退職金と合算して控除を最大限に活かすことが可能です。ただし、受け取りのタイミングが重なると控除枠を圧迫する可能性もあるため、受給時期を分けるなど工夫が求められます。
退職金にかかる税金は、正しい手続きやタイミングを押さえることで、大きく軽減できる可能性があります。この章では、これらの制度についての知識を事前に把握しておくことで、手元に残る退職金額を最大化できます。
退職金を受け取る際に「退職所得申告書」を会社へ提出することで、本来受けられるはずの退職所得控除が自動的に適用されます。この申告書が提出されていないと、会社側は税務署の指示に従い、割高な税率で源泉徴収を行うため、必要以上に税金を差し引かれてしまうことがあります。
申告書を提出することで、控除額を正確に反映させることができ、不要な納税を避けることが可能です。万が一提出し忘れてしまっても、確定申告をすることで還付を受けられる場合があります。
退職後すぐに再就職したり副収入があったりすると、退職金とその他の所得が同じ年に合算され、課税対象が大きくなってしまう可能性があります。
退職金自体は分離課税ですが、医療費控除や配偶者控除などとの絡みで、合計所得金額が増えると控除額が減ることもあります。そのため、転職や再就職の時期を翌年以降にずらすことで、税負担の軽減が見込めるケースもあります。
税金の仕組みを理解し、タイミングを見極めることが、賢く資産を残すコツといえるでしょう。
退職した年に高額な医療費を支払ったり、ふるさと納税を行った場合、それらの支出を「所得控除」として活用することで、税金を軽減できるチャンスがあります。
特に、医療費控除は10万円または所得の5%を超えた分が対象となるため、退職後に手術や通院などの予定がある人は申告を忘れないようにしましょう。また、ふるさと納税は実質2,000円の負担で複数の自治体に寄付でき、税金の還付や控除に繋がります。
退職金との合わせ技で、控除枠を有効活用するのがポイントです。
退職金を受け取る際、多くのケースでは会社が源泉徴収を行い、確定申告は不要です。しかし、すべての人が申告不要というわけではなく、状況によっては確定申告を行うことで、税金が戻ってくる可能性もあります。
この章では、申告が必要かどうかの判断基準から、手続きの流れ、還付の可能性まで、わかりやすく解説します。
退職金に関しては、基本的に「退職所得申告書」を退職先に提出していれば、源泉徴収で精算されるため確定申告は不要です。
しかし、申告書の未提出や、年の途中で複数の収入がある場合などは、正しい税額計算のために確定申告が必要です。また、医療費控除や寄付金控除など、他の控除を適用したい場合も申告を通じて税金を取り戻せる可能性があります。
自身の状況に照らし、確定申告をすべきかどうかを早めに確認することが重要です。
退職金に関する確定申告を行うには、いくつかの書類が必要です。
主に用意するのは、下記になります。
医療費控除やふるさと納税を併用する場合は、その領収書や寄付証明書も揃えましょう。
毎年2月中旬〜3月中旬の期間内に行い、税務署への持参・郵送・e-Tax(オンライン)いずれでも手続き可能です。
申告に不安がある場合は、税理士や市区町村の無料相談も活用しましょう。
退職金を受け取った後に確定申告をすることで、すでに納めた税金の一部が戻ってくる場合があります。
例えば、退職所得申告書を提出していなかった場合や、医療費控除・寄付金控除などを使いたい場合、源泉徴収された税額が本来の税額を上回っていることがあります。また、年の途中で退職して収入が少なくなった人も、税額が過剰に計算されているケースが少なくありません。
こうした人は、確定申告を行うことで払い過ぎた税金の還付を受け取れる可能性があります。
退職金に対する課税は、支給日を基準として税額が決定されるため、退職のタイミングだけでなく受け取りのタイミングも慎重に考える必要があります。これまでの税制改正や、今後予定されている見直しによって、短期勤続者や複数回退職する人への影響も強まってきています。
退職所得控除や確定拠出年金制度をうまく活用することで、税負担を大きく減らすことも可能です。また、確定申告によって税金が還付されるケースもあるため、自分が対象かどうかを早めに確認しましょう。
将来の資金計画を左右する重要なポイントとして、退職金の税務知識を正しく身につけておくことが大切です。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。