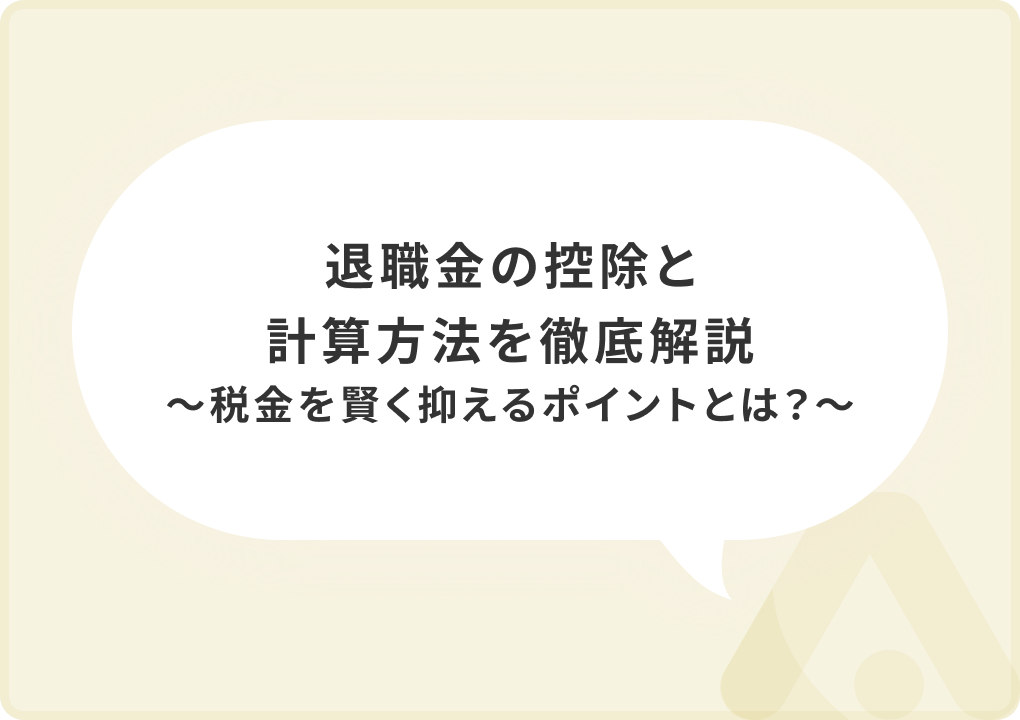
退職金運用



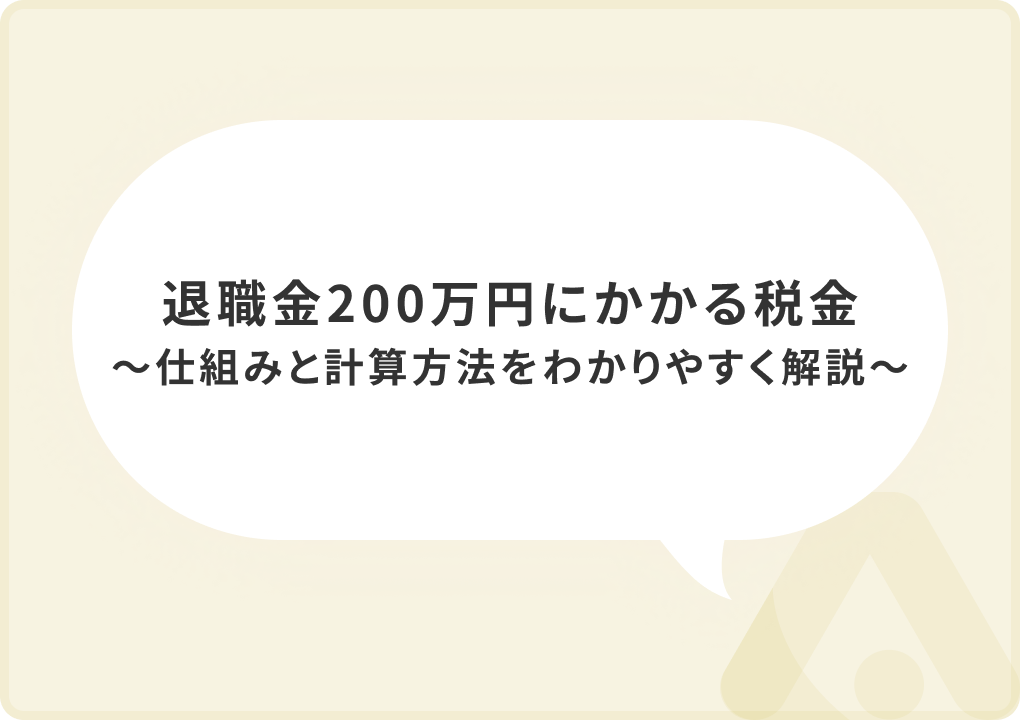
退職金200万円を受け取る場合、税金がどれだけかかるか気になりますよね。退職金には退職所得控除や1/2課税といった特別な優遇措置があるため、実際の手取り額はケースによって大きく変わります。
本記事では、所得税・住民税・復興特別所得税の仕組みや金額の計算方法をはじめ、勤続年数や受け取り方による違い、確定申告の必要性について詳しく解説。退職金を賢く受け取るために必要な知識がしっかり身につきます。
目次
退職金は毎月の給与と違い、「退職所得」として特別な税制度が適用されます。この制度では、長年の勤務に対する配慮として、一定額の控除が設けられており、さらに課税対象は実際に受け取った金額の50%に抑えられるという大きな優遇があります。
ただし、どんな場合でも非課税になるわけではありません。受け取り方や勤続した年数によって、税金のかかり方は変わってきます。
こうしたルールをしっかり理解しておくことで、余計な納税を避け、効率的に資金を確保できます。
退職金を受け取るときには、以下の3種類の税金が関係します。それぞれの仕組みを押さえておきましょう。
退職金は、他の給与や副業収入などとは異なり、「分離課税」という特別な課税方式が適用されます。
これは、年間の合計所得とは切り離して税額を計算する方法で、年収が高くても退職金だけに別の税率が適用されるのが特徴です。
さらに、退職所得控除を差し引いた残りの金額についても、課税対象額が半分に圧縮されます。この1/2課税により、同じ金額を一時的に受け取っても、通常の収入よりも税金が少なくなるというメリットがあります。つまり、制度を理解していれば、手元に残る金額を大きく増やせる可能性があります。
退職所得控除は、退職金を受け取る際の税負担を軽減するために設けられた特別控除の制度です。
勤続年数に応じて非課税枠が広がる仕組みで、在職期間が長いほど控除額も増加します。退職金の多くを非課税で受け取るためには、この制度を正しく理解しておくことが重要です。
退職所得控除の金額は、在職年数に応じて計算されます。
具体的には、勤続20年以下であれば「40万円×年数」、20年を超える部分については「70万円×超過年数」を加算します。
例えば、勤続25年なら「40万円×20年+70万円×5年=1,550万円」が控除額です。この計算式をもとに、退職金の非課税枠がどれくらいあるかを事前に把握しておくことが、節税の第一歩となります。
退職所得控除には最低保証額があり、勤続年数が1年未満でも最低80万円の控除が適用されます。
例えば、半年勤務でも80万円までは非課税となるため、短期間の勤務であっても税の軽減効果を得ることができます。また、障害者となったことにより退職する場合は、控除額にさらに100万円が加算される特例もあります。
このような加算ルールを理解することで、より有利に退職金を受け取るための準備ができます。
退職金として200万円を受け取る場合、「実際の手取り額はいくらになるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。退職金には退職所得控除や1/2課税といった優遇措置があり、通常の給与と比べて税負担はかなり抑えられます。
本項では、退職金の税金を計算する際の流れを、3つのステップに分けて丁寧に解説します。税額の概算を知ることで、将来の資金計画にも役立てることができます。
退職金の税金を計算する最初のステップは、「課税退職所得金額」の算出です。まず、退職金から退職所得控除額を差し引き、残った金額の50%が課税対象になります。
例えば、退職金200万円に対し控除額が400万円であれば、差引きはマイナスになるため課税対象はゼロとなり、税金は発生しません。控除額によって税額が大きく左右されるため、勤続年数に応じた控除の確認が重要です。
課税退職所得金額が確定したら、次は所得税の計算に進みます。所得税は金額に応じた累進税率が適用され、さらにその税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。
例えば、課税退職所得金額が50万円であれば、5%の税率が適用され、所得税は25,000円、復興特別所得税は525円となります。合計で約25,525円が税金として引かれる計算です。
正確な計算には税率表の確認が欠かせません。
住民税は、課税退職所得金額に対して原則一律10%が課税されます。
例えば、課税退職所得金額が50万円であれば、住民税は5万円です。なお、退職金にかかる住民税は、翌年6月頃にまとめて請求されることが多いため、受け取った年の手取りには影響しません。
受給後しばらくしてから納付通知が届く点には注意が必要です。余裕を持った資金管理をすることで、急な出費にも対応しやすくなります。
退職金にかかる税金は、勤続年数によって大きく変わります。退職所得控除は在職期間に応じて増えるため、同じ金額でも勤続年数が長いほど非課税になる可能性が高まります。
ここでは、具体的な勤務年数別に、税負担の違いを比較し、手取り額の目安を紹介します。
在職期間が5年以下の人が退職金を受け取る場合、「短期退職手当等」として分類され、特例の1/2課税が適用されない点に注意が必要です。
令和4年の税制改正以降、短期退職でも高額な退職金を受け取ると、そのほとんどが課税対象となってしまいます。
例えば、退職金が200万円で控除額が80万円なら、残りの120万円が全額課税されるため、実際の手取りが大きく目減りする可能性も。短期退職時こそ、控除額や課税方式を正しく把握することが大切です。
10年間勤務した上で200万円の退職金を受け取った場合、控除額は「40万円×10年」で計算され、合計400万円となります。
つまり、控除額が退職金額を上回るため、課税対象はゼロ。所得税も住民税も発生せず、退職金全額がそのまま手元に残ります。
このように、勤続年数が長くなるほど控除枠が広がり、実質的な手取り額が増えるのが大きな利点です。制度の仕組みを理解することで、賢く税負担を回避できます。
退職金の受け取り方には「一時金」と「年金形式」の2パターンがあります。どちらを選択するかによって、税金の計算方法や負担額に大きな違いが生じるため、慎重な判断が必要です。
一時金は分離課税の対象となり、退職所得控除と1/2課税の恩恵を受けられる一方、年金形式では雑所得として総合課税となるため、他の所得と合算されて税率が上がる場合も。
老後の収入計画に直結するため、自分に合った方法を選ぶ視点が欠かせません。
一時金として退職金を一括で受け取る場合、退職所得控除が適用されるほか、控除後の金額は1/2に軽減されて課税されます。
メリット
デメリット
受け取り時期や老後資金とのバランスを見極めたうえで選択することが肝要です。
年金形式で退職金を分割して受け取る場合、収入は毎年の「雑所得」として扱われ、総合課税の対象となります。
メリット
デメリット
年金形式は長期的な資金管理に適していますが、税金面では一時金より不利になることが多い点に注意が必要です。
退職金を受け取った際、200万円という金額であっても確定申告が必要になる場合があります。ポイントは「申告書の提出有無」と「退職金の受け取り方」です。
この章では、制度の仕組みを理解して、適切に対応しましょう。
退職金を受け取る際に会社へ提出する「退職所得の受給に関する申告書」
これは、税金面で非常に重要な書類です。申告書を提出していれば、退職金に対する税金は会社側で適切に計算・源泉徴収され、原則として確定申告は不要となります。
しかし、申告書を提出していないと、退職金全額に対して一律で約20.42%の税が源泉徴収され、結果的に払い過ぎとなることも。このような場合は、確定申告を行えば還付を受けられる可能性があります。
退職金を受け取った人でも、次のようなケースでは確定申告が必要になります。
確定申告は不要と思い込まず、条件をきちんと確認することが大切です。
退職金は「退職所得」として扱われ、一般的な給与と比べて税制上の優遇が用意されています。200万円という金額でも、勤続年数が10年以上あれば退職所得控除により非課税になるケースが多く、一方で5年未満の場合は短期退職手当等として重い課税が課されることもあります。さらに、一時金と年金形式では税負担の大きさが異なり、確定申告が必要かどうかも変わります。
受け取り方法・控除額・課税制度の3つを正しく理解し、自分にとって最も有利な選択をすることが、手取りを最大化するカギになります。
Share この記事をシェアする !
投資の相談や気になることがあれば、
Action合同会社までお気軽にお問い合わせください。
当ウェブサイトは、弊社の概要や業務内容、活動についての情報提供のみを目的として作成されたものです。特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームに関する申し出や勧誘を意図したものではなく、また特定の金融商品・サービスあるいは特定の取引・スキームの提供をお約束するものでもありません。弊社は、当ウェブサイトに掲載する情報に関して、または当ウェブサイトを利用したことでトラブルや損失、損害が発生しても、なんら責任を負うものではありません。弊社は、当ウェブサイトの構成、利用条件、URLおよびコンテンツなどを、予告なしに変更または削除することがあります。また、当ウェブサイトの運営を中断または中止させていただくことがあります。弊社は当サイトポリシーを予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。